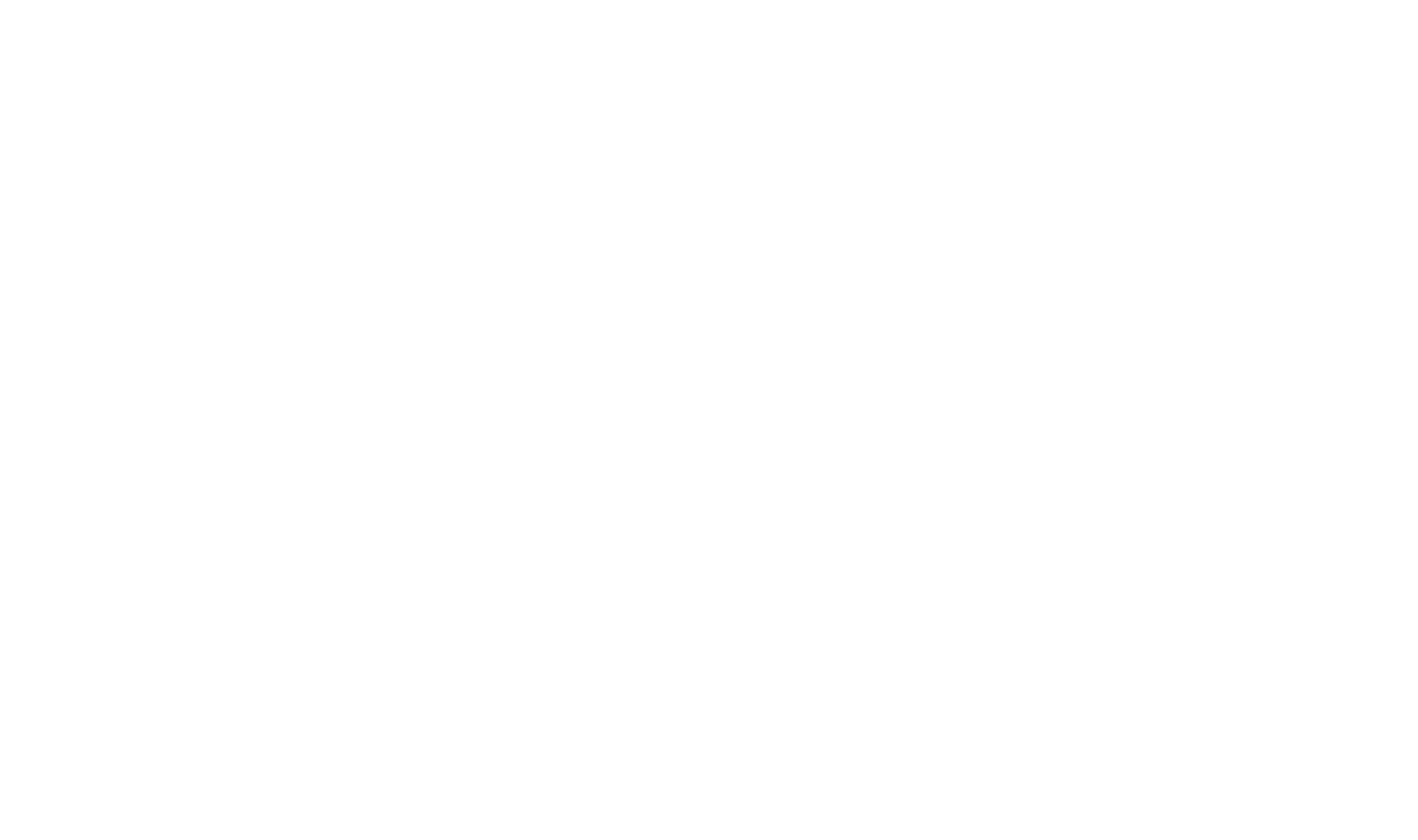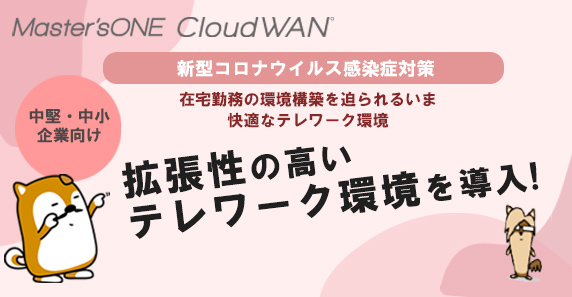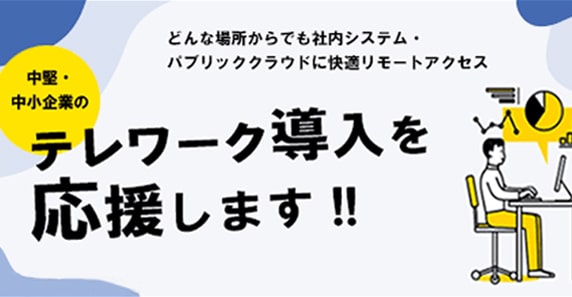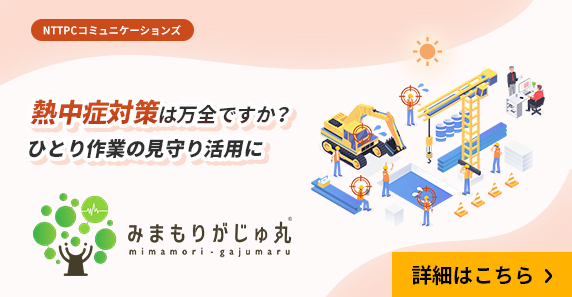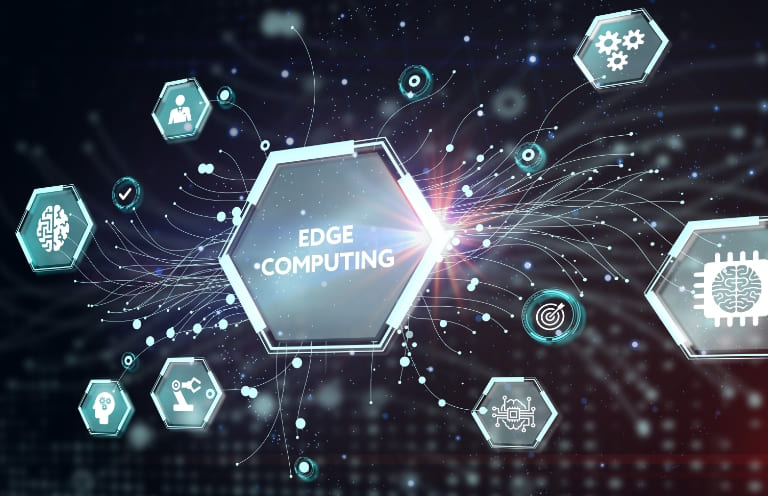BCP(事業継続計画)は中堅・中小企業こそ重要!対策ツールを紹介

この記事で紹介している
サービスはこちら
- 目次
BCP(事業継続計画)対策とは?
BCPとは地震や台風などの自然災害、事故や火災、コロナウイルス感染症の流行などのリスクに直面した場合でも、企業の受ける被害を最小限にとどめ、中核となる事業を継続および早期復旧させるための方法や体制などをまとめた事前計画のことです。
トラブルによる業務停滞・顧客流出は企業の信頼を損ない、廃業になる恐れもあり、BCP対策によるリスクヘッジは企業にとって必要不可欠な取り組みとなっています。
また、よく似た響きをもつ言葉に「BCM」がありますが、こちらはリスク発生時に実際に事業を継続できるよう管理・運用する手法を指します。具体的には、教育や訓練を通じ、BCPを机上の空論ではなく実のあるものとする活動などを指します。
とくに中堅・中小企業にとってBCP(事業継続計画)対策が必要な理由

さて、ここまでお読みになって「BCPは大企業向けのもの、中堅・中小企業にはあまり縁がない」という印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実は中堅・中小企業にこそBCP対策が必要です。
理由として、中堅・中小企業では通常時でも従業員数、設備、資金面など経営基盤が脆弱な場合が多く、トラブルが発生した場合、直ちに有効な手を打つことができず事業縮小や廃業に追い込まれる恐れがあることなどがあげられます。
リスク発生時にも顧客からは普段同様の対応が求められ、人・モノ・資金がさらに限られた中で速やかに復旧作業を終え、顧客のニーズを満たすには事前にきちんと計画しておく必要があります。
一例をあげれば、遠隔地や災害対策の施された場所に「業務データのバックアップ」を取っておく、本社以外の場所からも業務を継続できるよう「テレワーク対応・クラウド移行」を進めておくなどです。
そして、BCPには現在の事業環境を改善する効果もあることも見逃せません。実際に、中小企業庁が発行した「中小企業BCP支援ガイドブック」には、「BCPは災害対応能力を高めるだけでなく日常の経営改善にも役立つ」と明記されています。
データ保護・バックアップなどBCP対策で導入を検討すべきツール

ここで、NTTPCが提供するサービスの中から、データ保護やデータバックアップサービスなどBCPに役立つものをいくつか紹介します。
通信網やクラウドサービスの停止を避けるなら
自由に複数回線を切り替えられるMaster'sONE CloudWAN®がおすすめ
データを保護する手段として、クラウド上に保存する方法、遠隔地にバックアップを保存する方法などが考えられます。特長の異なる複数のパブリッククラウドをシームレスにつなぐ「クラウドコネクト」、自由なアクセス回線、自由なネットワーク設計を実現する「SD-WAN」機能を備えた「Master'sONE CloudWAN®」なら、様々な対策が可能です。
バックアップ、データ保護ならセキュアで免震設備を完備している
WebARENA® Symphonyがおすすめ
「WebARENA® Symphony」は、ISPサービスを提供するNTTPCだからこそ実現できる高速・低遅延・セキュアなネットワークを備えたデータセンターです。
データセンタービルの地下全体に免震装置を設置することでビルと地盤とを切り離し、震度7クラスにも耐えうる免震性能実現しています。
また、地下30m付近の強固な地層に鋼管杭を打設することにより、液状化対策も実施しています。
万一の災害発生時にも御社の大切なデータをお守りし、BCP対策をサポートします。
データセンターについてさらに詳しく知りたい方はこちら
データセンターとは?クラウドとの違い・メリット・料金体系を紹介
BCP対策関連サービス一覧
NTTPCでは上記のサービス以外にも、データバックアップ、コロナウイルス対策、情報セキュリティ対策、防犯対策などさまざまなソリューションを提供しています。詳しくは下記のページをご参照ください。
NTTPC BCP対策関連サービス一覧様々なBCP対策ソリューションを提供しています
事業継続に必要なBCP策定を5つのステップで紹介
では、具体的にどのような手順でBCPを策定すればよいのでしょうか?内閣府発行の「事業継続ガイドライン」を基に、大まかな手順を見てみましょう。ここでは、ガイドラインのⅠ~Ⅶの7章で説明されている内容を、5ステップに簡略化して説明します。

STEP1:BCP対策の重要性を理解し基本方針を策定する
(Ⅰ事業継続の必要性と基本的考え方・Ⅱ方針の策定)
まずはBCP対策の必要性およびメリットを再確認しましょう。そして自社が果たすべき責任、顧客が求めているもの等を分析し、事業継続に対する考え方を示す基本方針を定めます。通常は経営陣がこの役割を担うと良いでしょう。
基本方針が決まったら、委員会等、BCP対策に臨む体制を組織します。
STEP2:リスク分析・重要業務の切り分けを行い、目標を設定する
(Ⅲ 分析・検討・Ⅳ 事業継続戦略・対策の検討と決定)
次に自社の手掛ける事業を分析し、継続または優先的に復旧させる必要のある「重要業務」の切り分けを行います。また、発生しうるリスクを洗い出し、その発生の可能性、事業への影響度、被害の程度などを分析します。
最後に復旧までの復旧時間や目標復旧レベルを設定すればこのステップは終了です。
STEP3:策定した内容をBCPほか各計画に落とし込む
(Ⅴ 計画の策定)
前ステップまでに決定した内容を踏まえ、BCPを策定します。併せて、事前対策の実施計画、教育・訓練の実施計画、見直し・改善の実施計画も定めておきます。
STEP4:教育・訓練によりBCPを定着させる
(Ⅵ 事前対策及び教育・訓練の実施)
BCPを策定したらBCP対策は終了、というわけではありません。策定した事前対策が担当者により計画通りに実施されていることを確認します。
また、いざというときに確実に実行できるよう、教育・訓練を通じて経営者、役員、従業員など関係者全員へのBCPの定着を図ります。
STEP5: 定期的にBCPの見直し・改善を実施する
(Ⅶ 見直し・改善)
事業を取り巻く環境は刻々と変化します。BCMの陳腐化を防ぐため、定期的に点検を行い、見直し・改善を実施する必要があります。
BCPが実際に機能し目標復旧時間や目標復旧レベルを達成できるか、人事異動などの変化に対応しているかを確認し、継続的に改善を実施していくことが必要です。
なお、より詳しい策定方法および策定事例については下記をご参照ください。
行政による中堅・中小企業向け「BCP実践助成金」を受け取ることができる

中堅・中小企業のBCP対策に対し、自治体などが助成金を用意しているケースもあります。
例えば公益財団法人 東京都中小企業振興公社では、BCP実践に必要な設備等の導入に関する経費の一部を最大1500万円まで助成する「BCP実践助成金」を設けています。
他にも長岡市、郡山市などの自治体がBCP策定に対して補助金を設けています。BCP対策をお考えの場合は、該当する自治体の補助金について調べてみてはいかがでしょうか。
BCP 対策により経営上の効果を得た事例
最後に、前述の「中小企業BCP支援ガイドブック」より、BCP対策により通常時の経営においても効果を得た事例を3つ紹介します。
IT 化とスペース効率化につながった事例
BCP対策に伴い、従来の紙媒体での保管を可能な限り電子データでの保管へと切り替えました。その結果、データの検索が可能となったほか、保管スペースが不要となり業務の効率化につながりました。
従業員のスキルアップにつながった事例
BCP対策の一環として、リスク発生時に従業員が出社できない場合でも事業を継続できるよう、代替要員の確保を決定。2年程度の周期でのジョブローテーションを実施し、従業員の多能工化を図りました。その結果、従業員のスキルアップにより一人当たりの生産性が向上しました。
生産効率向上につながった事例
以前は各工程に必要な作業を理解し習得するまでに多くの時間を要していましたが、BCP対策に伴い、誰しもが作業できるよう生産工程の簡略化および改善を実施しました。その結果、必要人員が減少し、コスト削減へとつながりました。
まとめ
BCP対策は中堅・中小企業にこそ重要であり、平常時の経営にも効果をもたらすものです。日常の業務をこなすだけでもご多忙のこととは思いますが、時間を割くだけの価値は十分にあるものと考えられますので、策定を検討してみてはいかがでしょうか。
※ICT Digital Columnに記載された情報は、リリース時点のものです。
商品・サービスの内容、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。