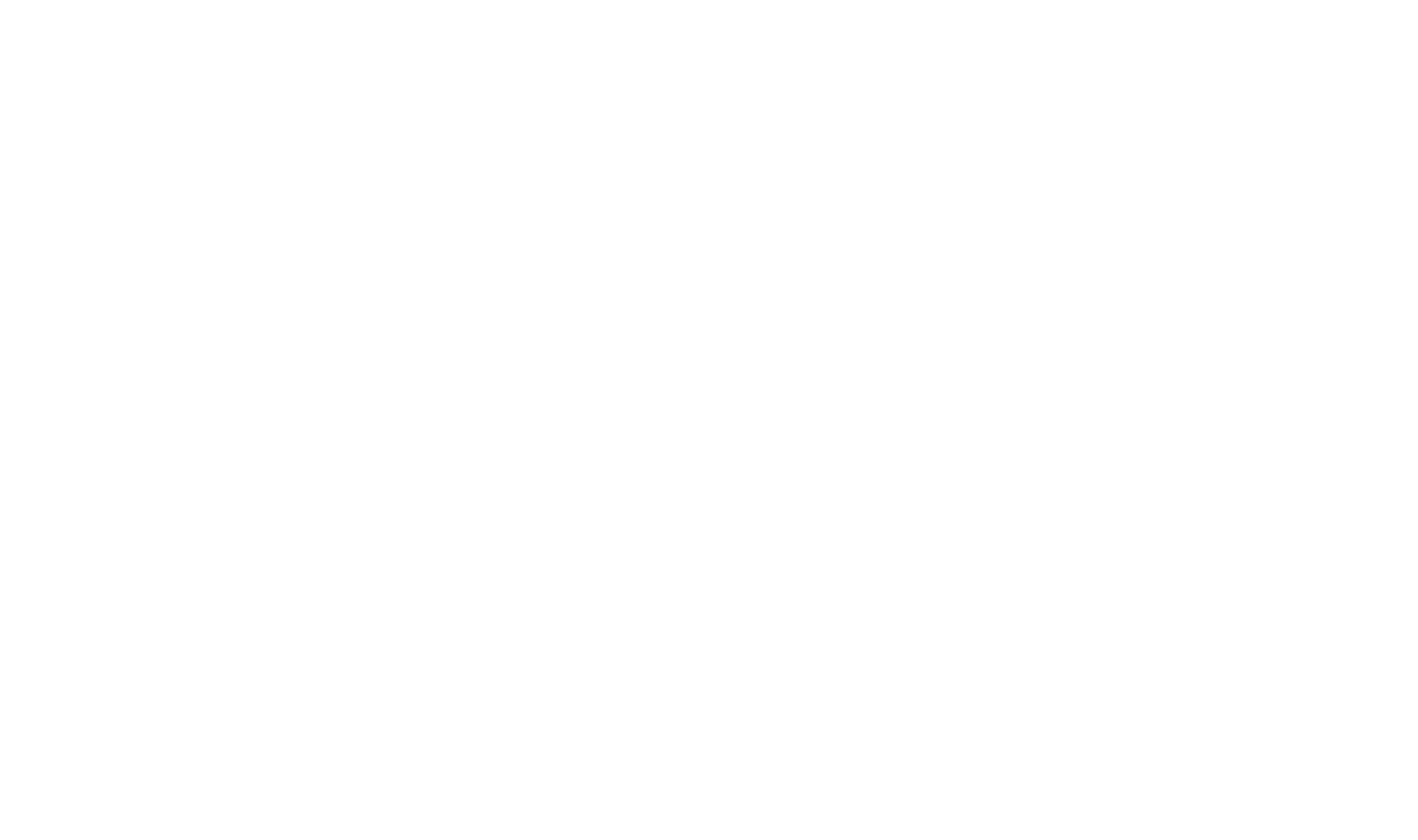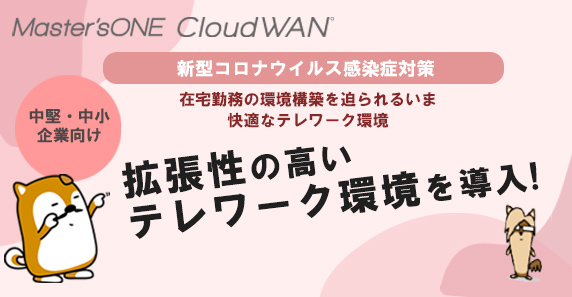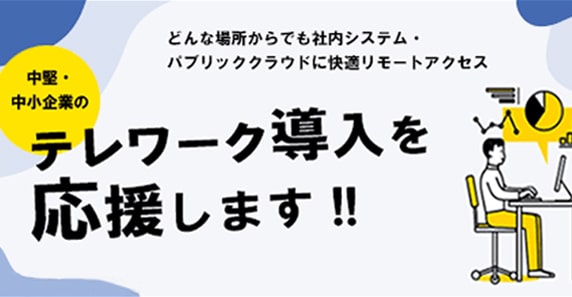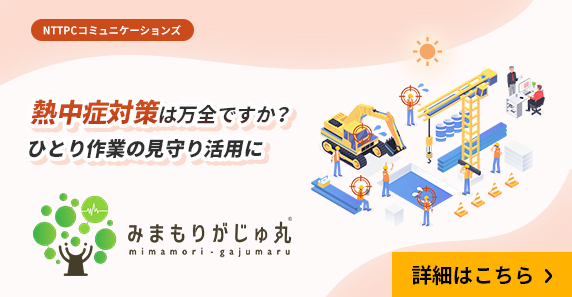【おすすめサービス紹介】テレワークのメリット・デメリットの解決方法

総務省のサイトでは、雇用側テレワークを「在宅勤務」「モバイルワーク」「施設利用型勤務」の3つの形態に分類しています。今回は、そうしたテレワークのメリット・デメリットをそれぞれ3つ紹介したうえで、デメリットを解決する方法について考えます。
- 目次
テレワークとは?
総務省のWebページでは、テレワークを「ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」と定義したうえで、その形態を「雇用型」「自営型」に大別しています。
「自営型」は個人事業者や小規模事業者等が行うテレワークを指し、さらに他人が代行することが難しい業務を行う「SOHO」と、他人が代行することが可能な業務を行う「内職副業型勤務」に分けられます。
雇用型テレワークの種類
一方、雇用型テレワークは企業に勤務する被雇用者が行うテレワークを指し、さらに就業場所に応じて「在宅勤務」「モバイルワーク」「施設利用型勤務」に分けられます。
| 在宅勤務 | 自宅が就業場所とするもの |
|---|---|
| モバイルワーク | 施設に依存せず、いつでもどこでも仕事ができる状態なもの |
| 施設利用型勤務 | サテライトオフィス、テレワークセンター、スポットオフィス等を 就業場所とするもの |
「在宅勤務」には通勤時間が不要となるほか、家事や子育て、介護などとも両立しやすいという特長があります。
「モバイルワーク」は移動中に業務を行うテレワークで、新幹線や飛行機の座席、駅や空港のほか、移動中に喫茶店などに立ち寄り業務を行う場合を含みます。
「施設利用型勤務」には所属する企業が用意した施設に勤務するもの、民間企業などが貸し出しているコワーキングスペースなどを自分の意思で借りるものの2種があります。
テレワーク導入による企業側のメリット

では、テレワーク導入によるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。まずは企業側について見てみましょう。
オフィスコストの削減
在宅勤務などの導入によりオフィスへの勤務者が減少すれば、それに比例して事務机や個人用ロッカーなどの必要数も減少します。結果的にオフィスの必要面積も少なくなるため、オフィスの維持費を低減することができます。テレワークと共にフリーアドレス制などを採用すれば、さらに事務机の数を減らすことも可能でしょう。
それに加えて、テレワークに伴う書類の電子化によりコピー用紙などの事務用品のコストも削減できます。
人材不足の解消
人口構造が急激に変化するなか、現在多くの産業において人手不足・後継者不足が問題となっています。テレワークの導入により柔軟な働き方が実現すれば、就業場所や居住地の制約も緩和されるため、多様な人材の確保が可能となります。
また、転居や家族構成の変化により有能な人材が退職し流出してしまうことを防止することにもつながります。
事業継続性の向上
特定のオフィスに社員全員が集合して業務にあたっているような場合、万が一そのオフィスが被災してしまった場合には業務の継続が困難となります。
在宅勤務、施設利用型勤務などのリモートワークが浸透していれば、そのような場合においても就業可能な人員により事業を継続することができます。リモートワークの導入により、BCP(事業継続計画)の策定もより実効性のあるものとなるでしょう。
テレワーク導入による従業員側のメリット

次に従業者側のメリットについて見てみましょう。
就業機会の拡大
テレワークの特長として、「時間や場所にしばられない」という点があります。短時間しか業務にあたれない、遠隔地に住んでいるため通勤が困難など、優秀なスキルを持ちながらも今までは就業が困難だった方々にとっては、就業機会の拡大につながることが期待されます。
また、移動が困難な高齢者・障がい者等の就業機会も拡大するでしょう。
労働環境の向上
これまで、労働環境はほとんど企業側が用意するものとされてきました。しかし、テレワークでは自ら業務にあたる環境を選択したり、構築したりといったことが可能となります。また、在宅勤務や施設利用型勤務では通勤時間も短縮されるため、それにかかる精神的・肉体的負担も軽減されます。
こうしたことから労働環境が向上し、集中力や仕事への意欲が促進され、生産性が向上する例もあるようです。
ワーク・ライフ・バランスの実現
少子高齢化の進む現代、家族が安心して子どもを育てられる環境を実現することは急務と言えます。在宅勤務を導入すれば、出産・育児・介護などによりやむを得ず辞職する、などのケースはかなり減少すると予想されます。
また、家族と触れ合う時間を確保したり、自己啓発や習い事など自己研鑽にかける時間を増加させたりすることも可能です。
テレワーク導入による企業側のデメリット

テレワーク導入にあたっては、気をつけるべきことも複数あります。
続いて企業側のデメリットについても見てみましょう。
セキュリティの強化が必要
在宅勤務やモバイルワークの実現には、社外から社内の業務システムに安全にアクセスする仕組みが必要となります。
従来の「社内ネットワークは安全、社外からの攻撃さえ守れば良い」という境界型セキュリティから一歩進み、社内・社外に関わらず全てのアクセスを信頼しない「ゼロトラスト」の考え方に基づいたセキュリティの強化が必要となるでしょう。
テレワーク環境構築へのコスト負担
テレワークの実施にあたり必要となる環境はセキュリティの強化だけではありません。テレワークに使用するノートPCなどモバイル機器の確保、ネットワーク環境の整備、電子決済システムなど業務関連ソリューションの導入など、テレワーク環境の構築にはさまざまコストが必要となります。
そのため、全国で行政などによる支援・補助なども用意されています。少しでもコスト面で負担を軽減するため、補助金の活用を検討してみましょう。
労務管理の複雑化
テレワークを開始すると、多くの企業は労務管理およびマネジメントの問題に直面することになります。
特定のオフィスに社員全員が集合して業務にあたっている場合には各社員の出社時間・退勤時間はもちろん、いつどれだけ休憩時間を取ったか、どれだけ集中して業務にあたっているかを直接的に確認することができます。しかしテレワークでは、労務管理システムの導入など代替手段が必要となることもあるでしょう。
テレワーク導入による従業員側のデメリット

テレワーク導入にあたっては、従業員側にも気をつけるべきことも複数あります。
従業員側のデメリットについても見てみましょう。
ネットワーク環境の整備が必要
自宅でのメールやインターネット閲覧と比較して、業務においてはより複雑な処理を必要とする業務アプリケーションを利用したり、容量の大きなファイルを送受信したりといったケースが発生します。在宅勤務を選択する場合には、接続環境や回線速度を見直すことが必要となるかもしれません。
また、在宅勤務においてももちろんですが、特にモバイルワークにおいてはセキュアな接続環境も必要となります。
作業環境の構築が困難
在宅勤務を思い立ったとしても、スムーズに作業環境を構築することは困難かもしれません。単身者であっても、仕事とプライベートとを完全に分ける作業環境を構築することは困難でしょう。
また、同居する家族がいる場合にはさらに複雑です。業務に集中できる部屋や家具、雑音が入らず電子会議に参加できる場所などを確保することは想像以上に困難です。また、家族の理解を得ることも重要なポイントとなります。
コミュニケーションの不足
ビジネスの基本として「報告・連絡・相談」、いわゆる「ホウレンソウ」がありますが、リモートワークではこれらを対面ではなくオンラインで行う必要があるため、ハードルは一段階上がると言えます。実際に、普段であればそばにいるITに詳しい社員に相談できていたことを相談できなかったために、マルウェアやランサムウェアに感染した例などもあるようです。
また、特に営業部門などでは、顧客とのコミュニケーションや訪問機会が減少し業務に支障をきたす場合もあるでしょう。
テレワーク導入を支援するおすすめICTサービス
NTTPCでは、企業のテレワーク導入を支援するICTサービスを用意しています。
セキュリティ・安定したネットワーク通信の両方を改善できる
セキュアアクセスゲートウェイサービス
「Secure Access Gateway(セキュアアクセスゲートウェイ)」は、在宅勤務、モバイルワーク、施設利用型勤務のすべての雇用型テレワークにおいて、安全・快適なネットワーク通信を実現するサービスです。
「ゼロトラスト」の考え方に基づき、個人所有の端末を使用してテレワークにあたる場合でも、社員を不正サイトへのアクセスやマルウェア・ランサムウェアへの感染から保護します。
また、既存の回線をそのまま利用するオーバレイ型のSD-WAN機能により、安定したネットワーク通信を実現します。
まとめ
今回はテレワーク導入におけるメリット・デメリットを企業側・従業員側の双方からまとめるとともに、デメリットを解消できるソリューションを紹介しました。
御社にとって効果的、効率的なテレワークの導入を実現するため、今回の記事を参考にして必要な施策、サービスについて検討してみてはいかがでしょうか。
※ICT Digital Columnに記載された情報は、リリース時点のものです。
商品・サービスの内容、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。