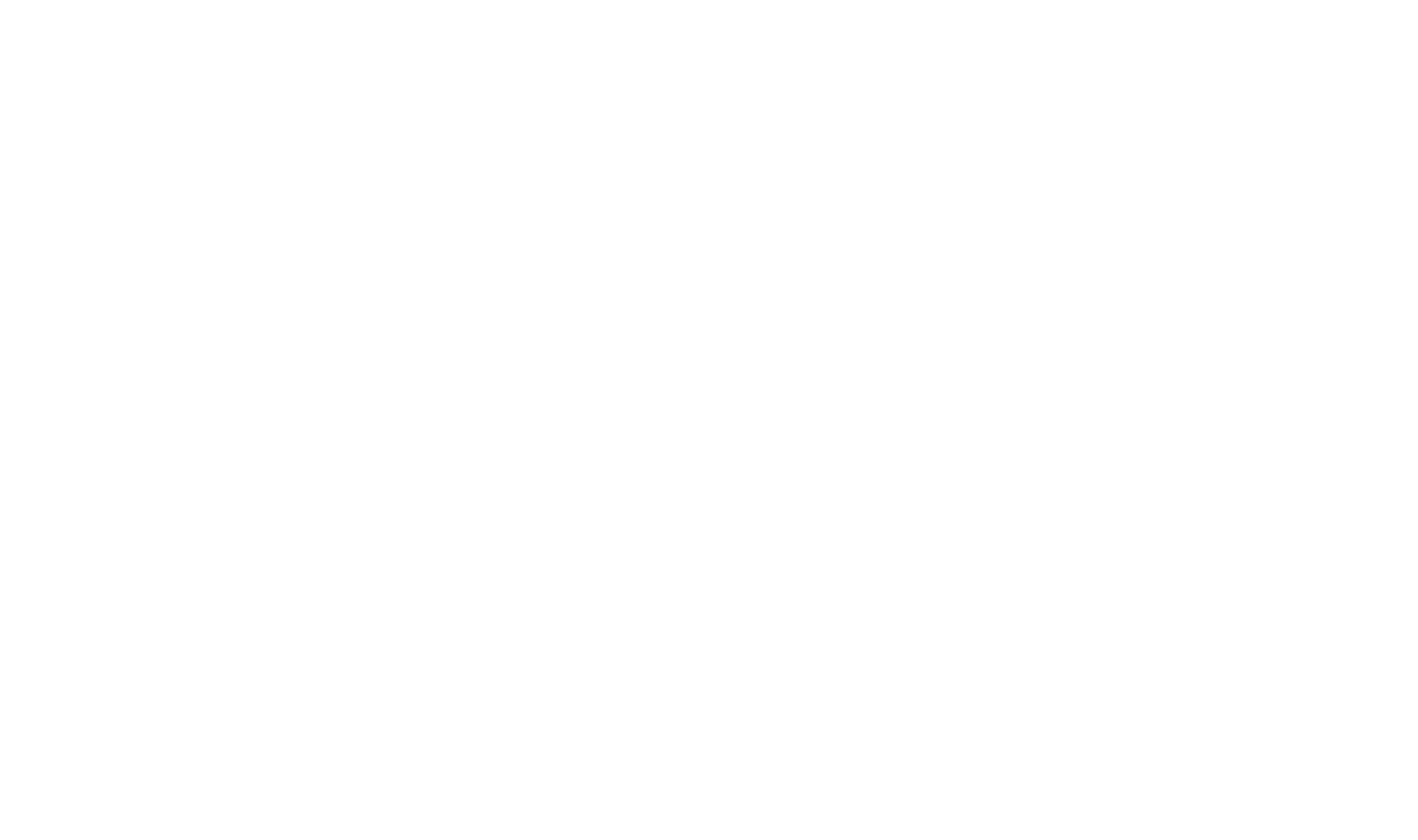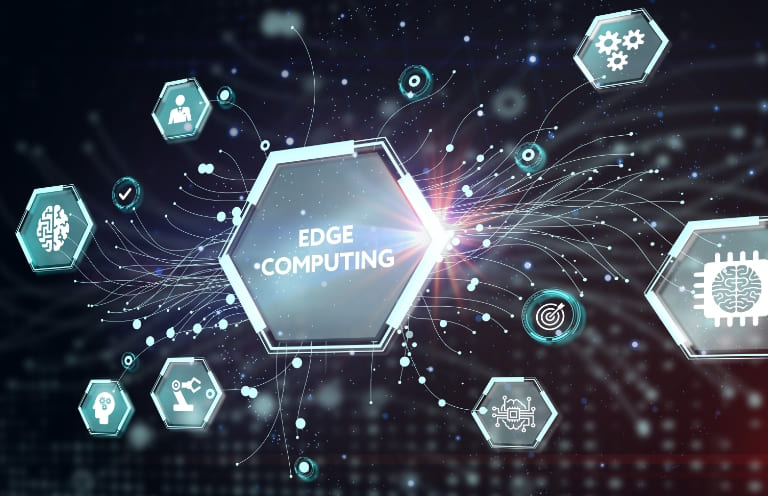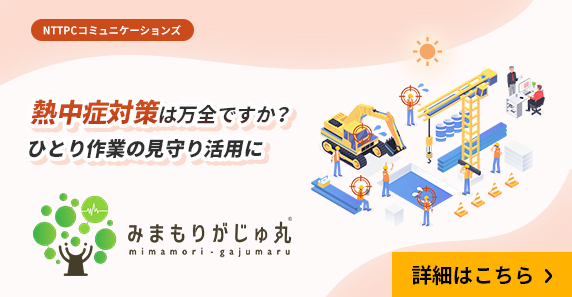ウェアラブルデバイスとは?種類や企業の活用事例を紹介

スマートウォッチを始めとする「ウェアラブルデバイス」は、従業員の健康管理や職場環境の改善などを目的として、製造業や建設業、流通業などの分野で導入が進んでいます。今回はウェアラブルデバイスの種類や機能、導入するメリットなどを紹介します。
この記事で紹介している
サービスはこちら
- 目次
ウェアラブルデバイスとは「手首や頭などに装着する小型端末」
「ウェアラブルデバイス(wearable device)」は、直訳すると「身に付けられる機器」の意味です。スマートフォンやタブレット端末のように手で持ったり机へ置いたりした状態で使用する機器とは違い、手首や頭など、身体に直接装着して使用する小型のコンピューター端末のことを指し、「ウェアラブル端末」と呼ばれることもあります。腕時計型のスマートウォッチや、メガネ型のスマートグラスなどが具体例です。
ウェアラブルデバイスが急速に普及した背景には、技術の進歩によりCPUやメモリなどコンピューターを構成する部品の小型化・低価格化が進んだこと、健康への意識が高まったことなどがあります。
総務省「情報通信白書令和6年版」によると、世界のウェアラブルデバイスの市場規模は2023年時点で400億円を超えており、2026年には500億円を超えると予測されています。また、国内に関しても2022年には38万台であったスマートグラスの出荷台数が、2025年には102万台まで増加すると予測されています。
ウェアラブルデバイスでできることとその可能性
生体情報収集のほか、通知・通話やGPSなどの機能も装備
ウェアラブルデバイスの機能は製品によって異なりますが、主に次の2点があげられます。
1つめは歩数や心拍数などの生体情報の収集です。GPS機能により位置情報を取得することも可能なため、移動距離や消費カロリーを計算するなど健康管理に役立てることができます。
2つめはスマートフォンなどの端末との連携機能です。通話やメッセージの送受信、電子決済などのスマートフォンの機能をウェアラブルデバイス上で利用することができます。
そのほか、デバイス単体でゲームや音楽再生などの機能を利用できるものもあります。
ビジネス・医療の分野では、職場環境の改善や治療への活用も
ウェアラブルデバイスをビジネスや医療現場で活用しようという動きも広がっています。
ウェアラブルデバイスは装着するだけで煩雑な操作をしなくても心拍数や体温などの生体情報をリアルタイムで収集できるため、職場環境の改善や治療などに活用することが可能です。
また、ハンズフリーで通話などの機能が利用可能なため、作業中のコミュニケーションツールとしての活用も可能です。さらに表示機能の充実したデバイスであれば、動画によるコミュニケーションや電子書類の確認などにも使用できます。
ウェアラブルデバイスを企業が導入する3つのメリット
1. 作業の効率化や生産性の向上につながる
ウェアラブルデバイスのGPS機能により各装着者の位置情報を取得することができます。大人数が同時に現場作業にあたる場合や、作業エリアの範囲が広い場合でも、従業員全員の位置を瞬時に、リアルタイムで把握することができます。
また、移動経路を精査すれば巡回ルートの効率化や作業動線の見直しなど、作業の効率化や生産性の向上に役立てられます。さらに従業員の生体情報を加味すれば職場環境の改善にも活用できます。
2. 従業員の心身の状態を可視化できる
ウェアラブルデバイスの生体情報収集機能により、装着者の心身の状態が可視化できます。それにより本人すら無自覚な不調を発見し、早期対策につなげることができます。
また、転倒検知やSOS発信などの機能がついたウェアラブルデバイスであれば、いざという時の対処も迅速に行うことができます。
3. 離職率の低下へ向けた対策が行える
前述のようにウェアラブルデバイスにより作業の効率化や生産性の向上、職場環境の改善が可能になれば、結果として従業員の健康維持に向けた適切なフォローや従業員エンゲージメントの向上、離職率の低下、燃え尽き症候群の防止などの効果が期待できます。
ウェアラブルデバイスの種類は主に4つ

腕時計・リストバンド型
スマートウォッチなど、手首に装着するタイプのウェアラブルデバイスです。
腕時計でいう文字盤にあたる部分がタッチ式ディスプレイになっており、時計機能やスマートフォンの通知確認機能などを持つものが一般的です。
心拍数や睡眠時間の計測など健康管理に役立つ機能を持つデバイスもあり、現在主流となっています。
指輪(リング)型
指に装着するタイプのウェアラブルデバイスです。
腕時計型・リストバンド型に比べて小型のため機能は限られますが、装着の負担が少なく、また手首に比べて細かい動作がしやすいという特長があります。
心拍数の計測など健康管理に役立つ機能や、電子決済機能を持つものが一般的です。ディスプレイは搭載されていないものの、スマホやPCとの連携によりデータの記録・管理なども行うようになっています。
メガネ・ゴーグル型
スマートグラスなど、メガネのように耳と鼻にかけたり、ゴーグルのようにベルトで頭部へ装着したりするタイプのウェアラブルデバイスです。
メガネのレンズの部分には液晶画面が搭載されており、地図を表示したり、視野内にある物品の情報を表示したりする機能を持つものが一般的で、業務効率化に活用することができます。また、VRやARの技術を使ったゲームや映像体験の機能を持つものもあります
スピーカー・イヤホン型
肩にかけたり、耳にはめたりして装着するタイプのウェアラブルデバイスです。
スマホなどの外部機器と無線接続し、ハンズフリーで通話できる機能を持つもの、脈拍数の計測など健康管理に役立つ機能を持つものなどが一般的です。
また、肩掛けタイプの一部には、カメラやセンサーが内蔵されていて装着者の位置情報や視覚情報を共有できるものもあり、工事現場などで働く作業者の安全を守るためなどに活用されています。
ウェアラブルデバイスを活用した、健康支援サービスも続々登場
みまもりがじゅ丸®
リストバンド型のデバイスを装着することで、脈拍や位置情報をリアルタイムに取得します。カメラや操作画面はなく、また複雑な操作も不要なため、運転中などにも負担なく使用できます。また、スマートフォンが使用できない現場にも導入可能です。
デバイスで取得した脈拍のデータから装着者の体調の変化を把握し、安全管理をサポートします。さらに、2025年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則により、事業者には熱中症対策が義務付けられることになりました。この中で、熱中症の恐れがある労働者を「見つける」ための措置として、ウェアラブル端末の活用も推奨されています。管理者には、熱ストレスや作業強度(身体への負担)を算出し、必要に応じてアラートを通知します。
また、転倒検知やSOS発信機能も備えており、一人作業者の見守りや安全リスクの低減にも寄与します。既存の環境温度センサーや勤怠管理システムとの連携も可能。熱中症対策など、作業者へのより高度な安全管理をお求めの企業さまにお勧めのサービスです。
健康経営®支援サービス
主にオフィスで働く従業員向けのサービスです。リストバンド型またはリング型のデバイスで仕事中のバイタル情報を計測します。
管理者側からは従業員個人のプライバシーを保護しつつ、部署やグループごとの健康状態を一目で確認できます。そのため、従業員自身ですら無自覚な心身の不調を客観的に把握でき、状態に応じて早期のセルフケアを促すことができます。また、収集したデータを統計的に分析することにより、プレゼンティーズム(心身の不調により業務効率が低下する状態)発生につながる心身への負荷を、組織のデータとしてタイムリーにとらえることができます。
また、スマホアプリで従業員が自分自身の分析結果を確認することもでき、従業員自身のセルフケアにも役立ちます。
各従業員の心身の状態の可視化や、職場環境の改善により生産性を向上したい企業さまなどにお勧めのサービスです。
【業種別】ウェアラブルデバイスを導入した企業の活用事例
製造業:各種アラート検出で、従業員への早期フォロー体制を構築
製造業では、作業巡回などの一人作業において本人以外が体調変化の兆しに気付きにくいという点がリスクとなっていました。ウェアラブルデバイスを導入して脈拍などの生体情報を取得することで、管理部門でも熱中症の危険性や身体への負担を把握することが可能となったほか、転倒などの際にはアラートが通知されるため、第三者によるフォローを迅速に行える体制を構築することができました。
合わせて、位置情報の時系列データを活用することで、巡回ルートの効率化も実現しました。
建設業:現場の安全管理・健康管理の向上が実現
地球温暖化などの影響により気温は年々上昇傾向にあります。40度を超えるような酷暑日も増加しており、それにともない熱中症患者も増加しています。
ある企業では、ウェアラブルデバイスの導入により、作業員のがんばりすぎを未然に防止することができるようになりました。また、管理部門と現場で作業にあたる従業員との間のコミュニケーションも増加し、より体調変化に意識が向くようになり、結果的に熱中症の発症を抑制することに成功しました。
また、蓄積されたデータをもとに従業員への対応や働く環境を見直すことにより、建設作業時の安全管理向上や労働環境の改善にもつながりました。
物流業:一人作業者の見守りで安全リスクを低減
物流業では車両運転や倉庫でのピックアップ作業など、基本的に一人で作業する機会が多くなっています。また、外気温よりも暑い倉庫や冷蔵庫内での作業もあり、急激な温度変化により体調に影響が出ることが懸念されます。
生体情報の収集機能に加えて転倒検知機能やSOS発信機能のついたウェアラブルデバイスを導入することにより、常に作業者の安全を見守ることができ、事故やトラブルが発生した際にもいち早く対応できるようになりました。
また、従業員自身もこれまで自身が無自覚だった体調の変化にも気付きやすくなり、セルフケアへの意識醸成を促すことにも成功しました。
全業種:部署やグループごとの健康状態を把握し、職場環境の改善を実施
ウェアラブルデバイスの導入により、管理部門では従業員の心身の状態を可視化して部署やグループごとに一覧表示できるようになりました。これにより従業員の心身両面でのフォローや職場環境の改善が可能となり、メンタル不調者などの減少につながりました。
また、本人が許容する範囲で、新入社員のデータを上長や人事担当者に開示することで、新入社員に負荷がかかり過ぎていないか、悩みを抱えていないかなどを把握でき、個別面談やワークショップを通じて自身の悩みや不安を打ち明けやすい環境を構築することができました。
まとめ
今回は「ウェアラブルデバイス」について解説しました。
腕時計・リストバンド型、指輪(リング)型、メガネ・ゴーグル型、スピーカー・イヤホン型などの種類があるウェアラブルデバイスには、生体情報収集のほか、通知・通話やGPSなどの機能があり、「作業の効率化や生産性が向上する」「従業員の心身の状態を可視化できる」「離職率の低下へ向けた対策が行える」などのメリットがあり、製造業、建設業、物流業を始めとする様々な業種で導入が進んでいます。
各従業員の心身の健康状態を客観的に把握したい、職場環境を改善したい、などをお求めの企業さまは導入を検討してみてはいかがでしょうか。
※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
※ICT Digital Columnに記載された情報は、リリース時点のものです。
商品・サービスの内容、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。