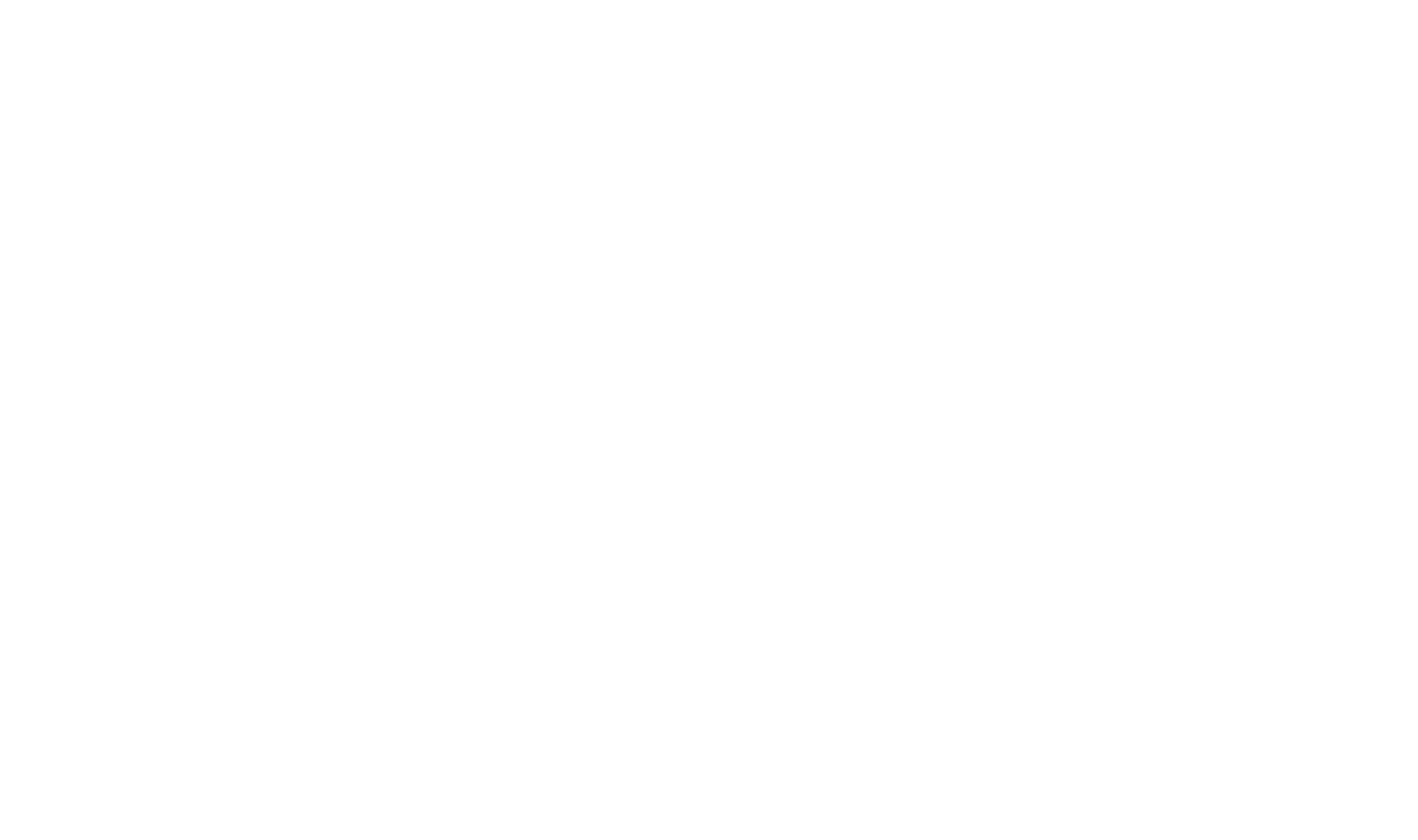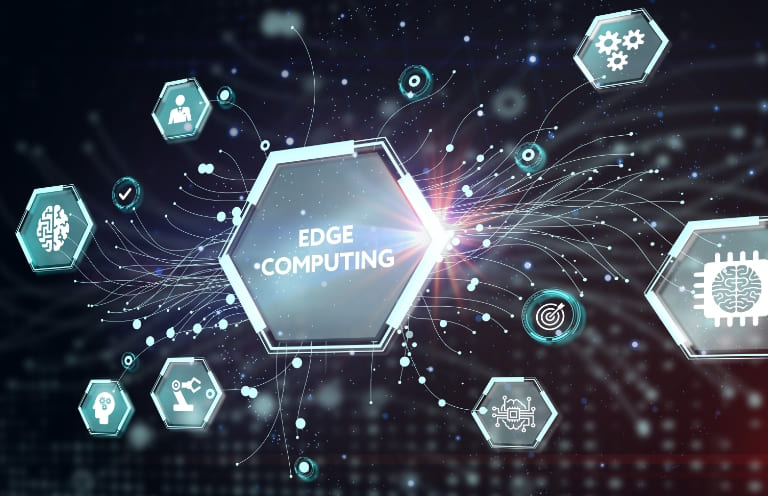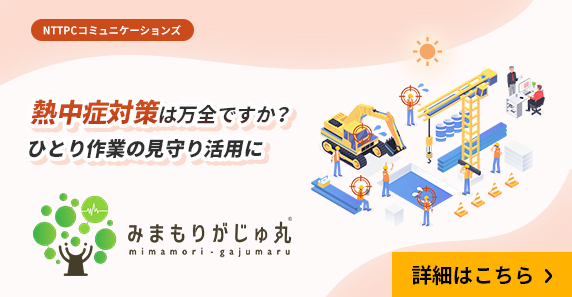レジリエンスとは?ビジネス上の意味と、向上を図る施策アイデア

今回は、精神的回復力を意味する「レジリエンス」について解説します。現在課題となっているメンタルヘルス問題の解決にはレジリエンスの向上が不可欠です。本コラムを参考として、レジリエンス向上の具体的方法や、企業が取り得る対策について学びましょう。
- 目次
レジリエンスとは「精神的回復力」を意味する心理学用語
レジリエンス(resilience)とは、心理学において「精神的回復力」と表現される言葉です。
もともとは物理学や工学において「回復力」や「弾性」などを表す英単語でした。バネを押し縮めたり引き延ばしたりした時や、低反発マットレスにくぼみを作った時に元に戻ろうとする力を指します。そこから転じて、ストレスや困難を受けた時に、それほどの困難をともなわずに乗り越え、回復する力を指して使われるようになりました。
さらに心理学分野以外にも、被災から復興する力を意味する「災害レジリエンス(防災レジリエンス)」、気候変動などに対して生態系が適応する力を意味する「環境レジリエンス(気候レジリエンス)」など、様々な分野でも使用されています。
また、ビジネス分野において企業や組織が社会および市場環境の変化によるリスク・困難を乗り越え適応する能力を意味する「組織レジリエンス」も現在注目を集めています。
「メンタルヘルス」や「ストレス耐性」との違いは?
レジリエンスと似た意味を持つ言葉に「メンタルヘルス」や「ストレス耐性」があります。
「メンタルヘルス」は「こころの健康状態」を意味します。メンタルヘルスをおびやかす事態に遭遇した時、速やかに乗り越え、メンタルヘルスを回復する個人の力がレジリエンスです。
「ストレス耐性」は「ストレスに対する抵抗力」を意味します。ストレスを受けたことにより変形した状態から回復する力がレジリエンスですが、そもそも変形しないような「硬さ・強さ」を意味する言葉がストレス耐性です。
現代社会におけるメンタルヘルスの課題と、レジリエンスの必要性
経済・産業構造の発展にともない、職場におけるメンタルヘルスの問題が顕在化しました。
厚生労働省の「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」によると、メンタルヘルスの不調により連続1ヶ月以上休業した、または退職した労働者がいた事業所の割合は13.5%と、前年の13.3%からさらに増加しています。
従業員の健康管理を経営的な視点から考える「健康経営」の観点からも、従業員のメンタルヘルス対策として従業員のレジリエンスを高めることが重要だと考えられ始めています。
参考:厚生労働省「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概要」
レジリエンスが高い人は、メンタルヘルスの不調に陥りにくい
レジリエンスが高い人の特徴として、いわゆる「自分の機嫌を取るのがうまい」点があります。自分の感情を上手にコントロールし、素早く気持ちを切り替えて楽観的に困難にあたることができます。また、「自分自身をよく理解している」点もあります。自分の長所を正しく理解し、目的意識を持って自律的に課題にあたることができます。さらに「自分および他者の価値を認める」点もあります。お互いの価値を認めて良好なコミュニケーションを保つことで、強固な協力関係を築くことができます。
こうした特徴から、レジリエンスの高い人は、メンタルヘルスの不調に陥りにくいといえます。企業として従業員一人ひとりのレジリエンスを高めることで、メンタルヘルス不調の発生リスクが抑えられ、結果として健康経営につなげることができます。
企業が従業員のレジリエンス向上へ取り組む「3大メリット」
企業が従業員のレジリエンスの向上に取り組むことにより、メンタルヘルス不調の発生リスクの低減に加えて、次のような大きなメリットを享受することができます。
職場環境が改善し、生産性の向上につながる
「自分および他者の価値を認める」という高レジリエンスの特長を手に入れれば、人間関係のストレスが軽減されます。また、同僚と強固な業務協力関係を築くことで、業務遂行能力も向上し、結果として企業全体の生産性向上が期待できます。
状況変化に強い企業風土が生まれる
多くの人にとって、業務環境の変化や異動は大きなストレス要因となります。「自分の機嫌を取るのがうまい」という高レジリエンスの特長を手に入れれば、そうした変化にも柔軟に対応できるようになります。また、突発的な災害や感染症の蔓延などの問題に対しても柔軟に対応できる企業風土が生まれるでしょう。
外部からの評価アップが期待できる
自社のレジリエンス向上への取り組みや従業員のレジリエンス評価を公表することにより、企業への評価アップが期待できます。企業への評価アップには、市場からの信頼を得やすくなる、製品のブランディングにつながる、優秀な人材を確保しやすくなる、などのメリットがあります。
レジリエンスを構成する6つの要素と、それぞれを高める方法
レジリエンス研究の第一人者であるペンシルベニア大学のカレン・ライビッチ博士によれば、レジリエンスは次の6つの要素(レジリエンスコンピテンシー)によって構成されているといいます。レジリエンスを高めるためには、それぞれのレジリエンスコンピテンシーを1つずつ高めていく必要があります。
1. 自己認識
「自己認識(Self-Awareness)」は、感情の傾向や考え方のクセなど、自分自身のことを正しく認識する力です。自己認識を高めるには、ヨガなど自分の内面をじっくり見つめる機会を設ける、他者が自分のことをどうとらえているかを知る機会を設ける、などの方法があります。
2. 自制心
「自制心(Self-Regulation)」は、自分の感情や衝動を抑える力です。自制心を高めるには、目標を決めて努力を継続できる仕組みを設けるなどの方法があります。また、怒りや悲しみといった感情の多くは相手に「裏切られた」と感じた時に生じますから、相手の思惑を正しく把握する訓練を行うことも有効です。
3. 精神的敏捷性
「精神的敏しょう性(Mental Agility)」は、気分を素早く切り替える力です。1つのタスクから別のタスクへ移るには小休止が必要となりますが、物事を俯瞰的に眺め、全体像を把握する習慣をつけることでその小休止を短くすることができます。
4. 楽観性
「楽観性(Optimism)」は、未来は必ず良くなる、自分で良くすることができる、という確信を持つ力です。楽観性を高めるには、自分のネガティブな思考を察知した上で、それをポジティブな思考に置き換えることが必要です。自分の内面を見つめられるような時間を設けるとよいでしょう。
5. 自己効力感
「自己効力感(Self-Efficacy)」は、「自分には能力がある」と自信を持つ力です。自己効力感を高めるには、自己の成功体験を積み重ねること、自分と似た境遇にある人の成功体験を疑似体験すること(代理経験)が必要です。各自の成功体験を認知するような場を設けることが有効です。
6. 他者とのつながり
「他者とのつながり(Connection)」は、他人との信頼関係を築く力です。他者とのつながりを強化するには、社内イベントや社外での活動など、他者と触れ合う機会を多く設けるなどの方法があります。まずは挨拶を習慣化するなどから始めてもよいでしょう。
具体的なアイデアは?レジリエンスを高める施策の例

レジリエンスの各要素を高めて従業員のレジリエンスを向上させるために企業にできる具体的な施策としては、例えば次のようなものが挙げられます。
レジリエンス研修を実施する
各機関より提供されているレジリエンス向上を目的とした専門の研修を利用する方法があります。研修には、メンタルヘルスやストレス、レジリエンスに対する理解の促進や、逆境に直面した時の感情をコントロールするスキルやコミュニケーションスキル向上などのプログラムがあります。
チャレンジを評価する制度を作る
自己効力感を高めるため、失敗を恐れずチャレンジし、成功体験を積めるような環境を整える方法もあります。具体的には、従業員のチャレンジを評価する仕組みを作る、業務上の失敗が許容されるような企業文化を醸成する、などの方法があります。
「心理的安全性」の高い職場づくりを意識する
「心理的安全性(Psychological Safety)」は、自分の意見や気持ちを安心して表明できる度合いのことです。自己効力感、他者とのつながりなどを向上させるためには、従業員が互いに称賛し合い、認め合えるような社内風土を醸成することが求められます。
健康経営に取り組む
各従業員のレジリエンスを高めるためには、そもそも心身が健康である必要があります。従業員の健康を確保するには、企業が従業員の健康確保のために投資する「健康経営®」への取り組みが最適です。健康経営にはメンタルヘルスの向上も含まれるため、レジリエンスの向上に取り組むこと自体が健康経営への取り組みの一環でもあります。生産性の向上、利用費負担の軽減、離職率の低下、企業イメージ向上などを目指すためにも、健康経営に取り組みましょう。
健康経営について詳しくは、「健康経営とは? 導入メリット・課題・取り組み方法」を参照してください。
レジリエンス施策の効果測定方法は主に4つ
従業員のレジリエンスを評価する尺度として、主なものを4つ紹介します。レジリエンスの向上に取り組む際には、これらの尺度を使って定期的に効果測定を行い、PDCAサイクルを回していくのがよいでしょう。
1. レジリエンススケール
「レジリエンススケール(Resilience Scale、RS)」は、Gail M. WagnildとHeather M. Youngによって1993年に開発された尺度です。「個人的コンピテンス(Personal Competence)」と「自己と人生の受容(Acceptance of Self and Life)」の2因子に関する25項目の質問事項に対し、1(強く反対)から7(強く賛成)の7段階で回答します。2010年には日本語版も発表され、有効性が証明されています。
2. 森らのレジリエンス尺度
「森らのレジリエンス尺度」は、森敏昭氏らによって2002年に開発された尺度です。自分を肯定的にとらえているかを測る「I AM因子」、自分を助けてくれる人がいるかを測る「I HAVE因子」、自分の能力に対する信頼感を測る「I CAN因子」、自分の将来に対する見通しを測る「I WILL因子」の4因子に関する29項目の質問事項に対し、「5=絶対にそう思う」から「1=絶対にそう思わない」の5段階で回答します。
日本の大学生向けに開発されたため、より本格的なレジリエンスの測定や施策の検討を行いたい企業に適しています。
3. 精神的回復力尺度
「精神的回復力尺度(Adolescent Resilience Scale、ARS)」は、RSを参考として、小塩真司氏らによって2002年に開発された尺度です。「新奇性追求」「感情調整」「肯定的な未来志向」の3因子に関する21項目の質問事項に対し、「5=絶対にそう思う」から「1=絶対にそう思わない」の5段階で回答します。「Adolescent(思春期)」の言葉が示す通り、若者向けの因子が中心のため、特にスタートアップ企業やベンチャー企業で活用しやすい尺度であるといえます。
4. 二次元レジリエンス要因尺度
「二次元レジリエンス要因尺度(Bidimensional Resilience Scale、BRS)」は、平野真理氏らによって2010年に開発された尺度です。「資質的レジリエンス要因」「獲得的レジリエンス要因」の2因子に関する21項目の質問事項に対し、「1まったくあてはまらない」から「5とてもあてはまる」の5段階で回答します。「自分は粘り強い人間だと思う」など質問内容も平易で、質問項目数も少ないため、まずは手軽に取り組んでみたいという企業でも取り入れやすい尺度です。
ITツールの活用で、データにもとづく"心身の状態の可視化"も可能に
レジリエンスの向上に取り組むにあたっては、各尺度による効果測定も重要ですが、それに加えて、従業員の心身の状態を可視化し管理する仕組みも必要となります。
例えばウェアラブルデバイスなどを活用し、生体データを収集する仕組みを作れば、従業員の心身の状態をリアルタイムで把握しつつ客観的なデータを蓄積することができます。
ウェアラブルデバイスを使用した「健康経営®支援サービス」
NTTPCの「健康経営®支援サービス」は、従業員の心身の状態を可視化できるITツールです。
従業員がリストバンド型またはリング型のウェアラブルデバイスを装着し、心拍の揺らぎデータを取得することで、自分の疲れやストレスの状態などを、アプリで客観的に確認したり、それをもとに早めのセルフケアを実施したりすることができます。
また、収集したデータは個人の情報を含まない統計的なデータとして、管理部門や人事部門で確認することもできるため、心理的負荷の状態を組織の変化としてタイムリーにとらえることができます。また、これらのデータをレジリエンス施策の検討・改善に活用することが可能です。
さらに新入社員に配布すれば、慣れない業務によるストレスに対するサポートや、メンタル不調への適切なケアのきっかけに活用でき、早期離職防止などにもつながります。
健康経営、レジリエンス向上にご興味のある企業さまにおすすめのサービスです。
まとめ
今回は、精神的な回復力を表す「レジリエンス」について解説しました。
従業員のレジリエンスを向上させれば、従業員のメンタルヘルスの不調を防ぐことができるとともに、職場環境の改善による生産性の向上や、状況変化に強い企業風土の醸成、ステークホルダーからの評価アップなどの効果が期待できます。
レジリエンスには「1. 自己認識」「2. 自制心」「3. 精神的敏捷性」「4. 楽観性」「5. 自己効力感」「6. 他者とのつながり」の6要素があり、レジリエンスを向上させるにはそれぞれの要素を高める必要があります。企業として「レジリエンス研修を実施する」「チャレンジを評価する制度を作る」「チャレンジを評価する制度を作る」「『心理的安全性』の高い職場づくりを意識する」「健康経営に取り組む」などを通じ、従業員のレジリエンス向上に取り組みましょう。また、今回紹介した各尺度などで施策の効果を定期的に測定し、PDCAサイクルを用いて持続的な向上を目指しましょう。
レジリエンス向上は健康経営にもつながります。健康経営の一環として、レジリエンス向上に取り組んでみてはいかがでしょうか。
※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
※ICT Digital Columnに記載された情報は、リリース時点のものです。
商品・サービスの内容、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。