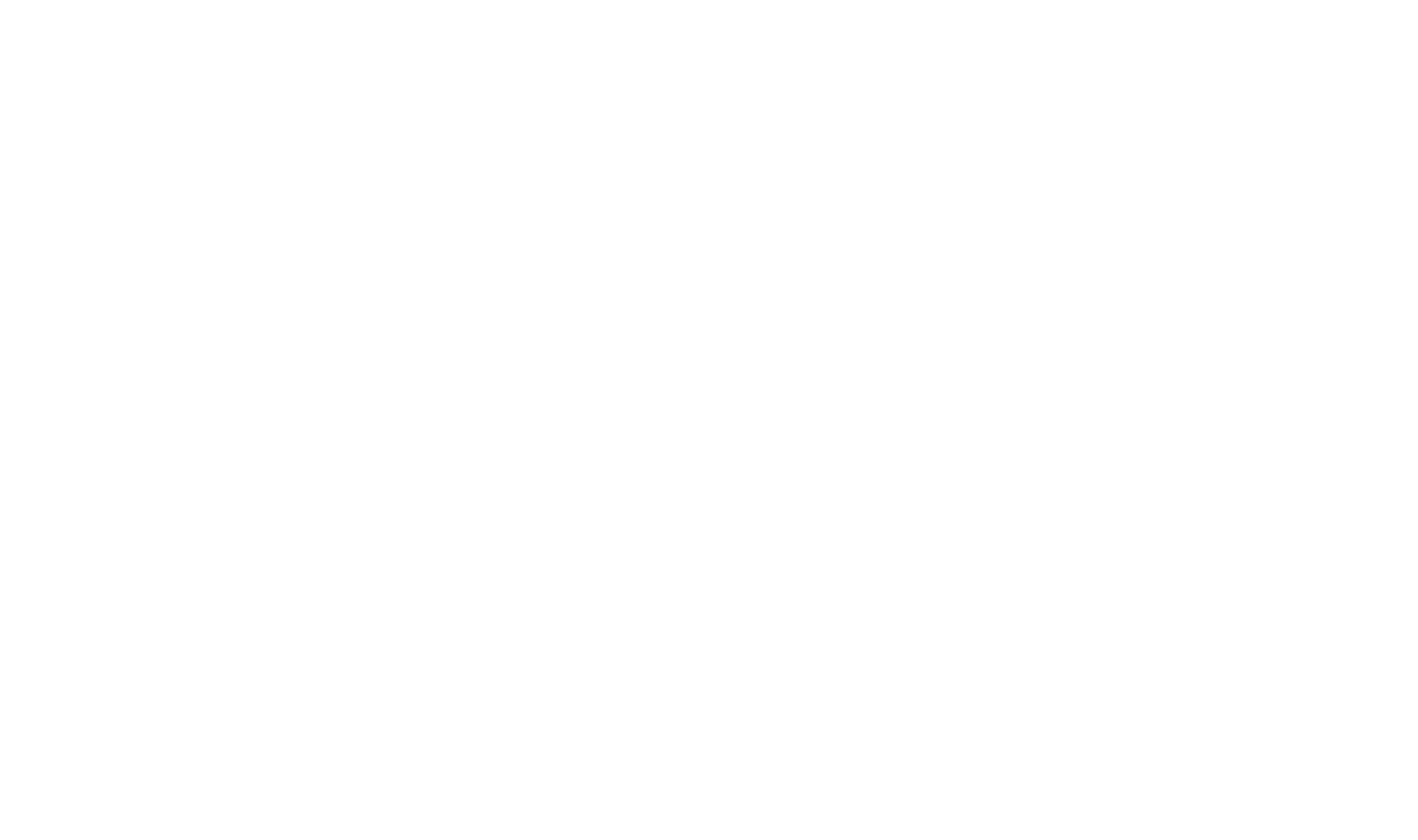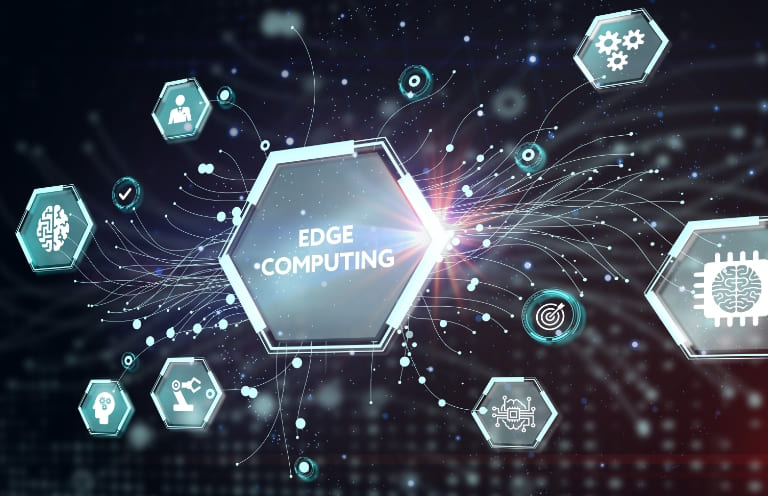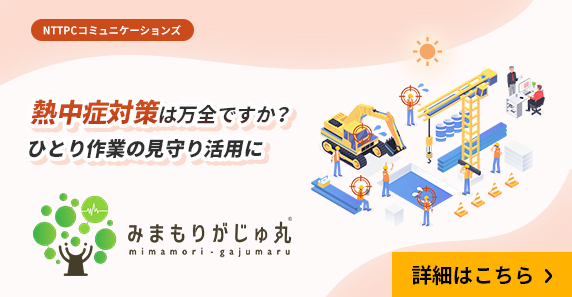プレゼンティーズムとは? アブセンティーズムとの違いと測定方法を解説

現在、健康経営への投資効果を図る指標として「プレゼンティーズム(presenteeism)」が注目されています。今回はこの「プレゼンティーズム」について、「アブセンティーズム」との違いや代表的な5つの評価方法などについて解説します。
- 目次
健康経営で注目される、「プレゼンティーズム」と「アブセンティーズム」
従業員の健康保持・増進に投資することにより、企業の収益性を将来的に高めることができるという「健康経営」は、2017年度より経済産業省による健康経営有料法人認定制度が開始されるなど定着が進んでいます。
近年では、投資したコストに対してどれだけの利益が得られたかを示すROI(Return On Investment、投資利益率)を健康経営に適用し、効果を実証する企業も増加しており、その際注目を集めている指標として「プレゼンティーズム(プレゼンティーイズム)」と「アブセンティーズム(アブセンティーイズム)」があります。
プレゼンティーズムとは、「健康問題が理由で生産性が低下している状態」のこと
「プレゼンティーズム(presenteeism、疾病就業)」は、健康に問題がある状態にも関わらず「会社にいる」状態を指します。欠勤には至っていないため勤怠管理上は表面化しにくいですが、生産性は低下しているため健康経営上においては問題となります。
具体的には花粉症、肩こり、不安感など、「休むほどではない」健康問題を抱えながら出勤している状態です。
アブセンティーズムとの違いは「出勤しているかどうか」
対して「アブセンティーズム(absenteeism、常習的欠勤)」は、健康問題が理由で欠勤、遅刻、早退などに至り、「会社にいない」状態を指します。健康経営上においてはプレゼンティーズムよりも大きな損失となりますが、勤怠管理により見出しやすく、対応も容易です。
両者とも健康問題を抱えている点は共通していますが、「出勤しているかどうか」に違いがあります。
プレゼンティーズムが企業に与える具体的な影響と重要性
経済産業省の「企業の『健康経営』ガイドブック」には、生産性損失コストのうち、プレゼンティーズムが実に8割近い77.9%を占めているという記載があります。
つまり、プレゼンティーズムを改善すれば労働生産性が大幅に向上する可能性があるわけです。企業にとって、プレゼンティーズムへの対策がいかに重要かが分かる数字といえるでしょう。
【評価手法】プレゼンティーズムによる影響度を可視化する、5つの測定方法
プレゼンティーズムによる企業経営への影響度(損失割合や労働機能障害の程度)を可視化する手段として、次の5つの評価方法が知られています。それぞれ従業員などへのアンケート調査で評価します。
1. WHO-HPQ
WHO-HPQは、WHO(World Health Organization - Health and Work Performance Questionnaire、世界保健機関-健康および業務パフォーマンスに関する質問票)が公開している質問票で、世界中で幅広く使用されています。2002年にロナルド・C・ケスラー氏により英語版が発表されたのち、フランス語、スペイン語、ポルトガル語など各国語に翻訳されており、2013年には日本語版も完成しています。
短縮版には7項目がありますが、そのうちプレゼンティーズムに関するものは「1. 同様の仕事をしている同僚の仕事ぶり」「2. 過去1~2年の自分の仕事ぶり」「3. 過去4週間の自分の総合的な仕事ぶり」の3項目です。それぞれ10段階で評価し、質問3を10倍したものを自分の主観による「絶対的プレゼンティーズム」、質問3を質問1で割ったものを他者との比較である「相対的プレゼンティーズム」と呼びます。
生産性損失コストを算出する際には相対性プレゼンティーズムが用いられることが多く、前述の経済産業省による生産性損失コストにも相対性プレゼンティーズムが用いられています。
2. SPQ東大1項目版
SPQ東大1項目版は、1項目のみで簡易的にプレゼンティーズムを評価できる質問票です。SPQは「Single-Item Presenteeism Question」の略で、日本語では「単項目プレゼンティーズム質問票」となります。経済産業省による平成27年度健康寿命延伸産業創出推進事業の中で、健康経営の枠組みによる健康課題の見える化の一環として東京大学ワーキンググループにより開発されました。
質問項目が平易で、「病気やけががない時に発揮できる仕事の出来を100%として過去4週間の自身の仕事を評価してください。」という1項目のみでWHO-HPQに匹敵する精度の評価を得ることができるとされています。その簡易さからか、経済産業省による2024年度健康経営度調査(従業員の健康に関する取り組みについての調査)によると、回答企業のうち2番目に多く活用されているWHO-HPQの15%の3倍以上、実に半数以上の53%がプレゼンティーズムの測定方法としてSPQを採用しているという統計があります。
具体的には、質問に対して例えば70%と回答した場合のプレゼンティーズムは1からその数値を減算した30%となります。
SPQはライセンスフリーで第三者による再利用が認められており、また研究目的および商用目的に無料で使用が可能です。
3. WLQ
WLQ(Work Limitations Questionnaire、就労制限に関する質問票)は、タフツ大学医学部が作成した評価尺度です。日本語版の「WLQ-J」は、日本初の健康問題による生産性低下率測定プログラムとしてSOMPOヘルスサポート株式会社により開発されました。算出アルゴリズムの信頼性が高く、米国では医学・健康などの分野で広く活用されている事でも知られています。
質問項目は時間管理に関するもの5問、身体活動に関するもの6問、集中力・対人関係に関するもの9問、仕事の結果に関するもの5問の計25問で、それぞれ「常に支障があった」~「全く支障はなかった」の5段階、または「私の仕事にはあてはまらない」から回答します。
アルゴリズムの詳細は公開されていませんが、例えば時間管理に関する項目では、「休憩を取らずに業務を続けることが難しかった」「日課やスケジュールを守ることが難しかった」などの項目があります。
4. WFun
Wfun(Work Functioning Impairment Scale、作業機能障害尺度)は、産業医科大学が開発した、健康問題による労働機能障害に特化した質問票です。心理測定学理論および数学理論にもとづいており、合計点のみで労働機能障害の程度を評価することができます。
質問は「ていねいに仕事をすることができなかった」など平易な7項目で構成され、1点~5点で回答します。
結果は合計得点(7点~35点)で評価され、合計得点が高いほど労働機能障害の程度が高いと判断されます。特に21点以上の場合は中程度以上の労働機能障害があると判断されます。
健康情報は用いられず、また性別や年齢、職種などに関係なく労働機能障害の程度を評価できるため、異なる企業間、異なる部署間での比較が可能であるという特長があります。
5. QQmethod
QQmethod(Quantity and Quality Method、量・質方式)は、トレーシー・ブラワー博士により1999年に開発された労働の質と量を同時に評価する方式です。まず持病など健康上の問題がないかどうかを診断したのち、症状がある場合のみ質問への回答を求めることで、プレゼンティーズムに対する評価を行います。あらかじめ健康上の問題について調査するため、プレゼンティーズムの原因を特定しやすい一方、健康上に問題のない場合にはプレゼンティーズムの存在を把握できないという欠点もあります。
質問は「仕事に最も影響をもたらしている健康問題」「過去3ヵ月で症状が出た日数」について具体的な回答を求めた上で、「症状がない時と比較した場合の仕事量」「症状がない時と比較した場合の仕事の質」について10段階の評価を求めます。生産性低下割合は1-仕事の量(0~10)×仕事の質(0~10)/100で求められます。
プレゼンティーズムの「具体的な損失額」を求める計算方法は?

プレゼンティーズムの解消や健康経営に向けた取り組みの効果を金銭的な側面から客観的に評価する方法として、「パフォーマンス低下度による損失額算定評価」と「健康関連総コスト換算による評価」の2つの方法があります。
1. パフォーマンス低下度による損失額の算定評価方法
プレゼンティーズムによる損失割合を元に、パフォーマンスの低下による生産性損失額を具体的に算定評価する方法です。
総人件費にWHO-HPQ、SPQ東大1 項目版、QQmethodを用いて算定したプレゼンティーズム損失額を掛けて損失額を算定します。必要とする調査項目が少ないため、簡易的に損失額を求めたい場合に便利です。QQmethodを用いる場合には、疾病歴より症状のあった日数を把握できるため、より正確な損失額を算定できます。
2. アブセンティーズムも含めた健康関連総コスト換算の評価方法
医療費、傷病手当金、労災補償費、アブセンティーイズムの日数×総報酬日額、プレゼンティーイズム損失割合×総報酬年額など、健康関連に費やされた合計のコストを求め、それを総人件費に乗じて生産性損失額を算定する方法です。
必要とする調査項目は多いですが、その分正確な損失額を求めることができます。
プレゼンティーズムの解消へ向けた、企業にできる「3ステップ対策」
プレゼンティーズムを解消するためには、次の3ステップの対策が重要となります。
Step1. プレゼンティーズムの現状を正しく把握する
まずは今回紹介した5つの測定方法などを活用して従業員にアンケート調査を行い、具体的な損失額算定評価を行います。評価を通じ、プレゼンティーズムの現状や程度を正しく把握したのち、具体的な目標設定を行いましょう。
Step2. 現状に合わせた健康経営施策を検討・実施する
続いてStep1で得たデータとその分析結果をもとに、健康経営につながる施策を検討・実施します。
具体的には、従業員が仕事の合間に軽い運動ができるような環境を整える、社員食堂のメニューを栄養のバランスが取れた体に良いものに変更する、休暇を取りやすい環境を整える、などが有効です。
Step3. 実施した健康経営施策を評価・改善する
プレゼンティーズムの対策は、一度実施して終了、ではありません。常にプレゼンティーズムの評価を行い、PDCAサイクルを回して効果を確認し、改善することが重要です。
また、プレゼンティーズムの測定データを分析する際には、特定の個人のデータによる評価の偏りがないよう、散布図を書き出すなど適切な方法を用いて正しい解釈を実現できるよう留意することが重要です。
プレゼンティーズム対策には、最新技術で計測した客観的なデータも活用を
ここまでお読みになり、「プレゼンティーズム対策は大変だ」と思った方もいるのではないでしょうか。プレゼンティーズムに対して適切な対策を採るためには、従業員の現時点での健康状況を正しく把握した上で、企業と従業員のそれぞれが実情に合わせた対策を行っていくことが重要となりますが、これは特に中堅・中小企業にとっては負担が大きいでしょう。
ただし、最新技術を適切に活用することで従業員現在の心身の状態を客観的なデータとして可視化し、プレゼンティーズムに対策する手段もあります。ここでは、一例としてNTTPCの「健康経営®支援サービス」を紹介します。
「健康経営®支援サービス」では、リストバンド型もしくはリング型のウェアラブルデバイスを通じて取得したバイタルデータをもとに、その日の自律神経のバランスや「集中」「ストレス」「疲れ」の状態が、スマートフォンアプリで視覚的に表示されます。各従業員が自身の心身の状態を客観的なデータとして把握でき、スマートフォンアプリ上でAIからのフィードバックを受け取ることで、従業員のセルフケアへの意識や行動変容へのモチベーションを醸成できます。
また、各従業員の詳細なデータは、プライバシー保護の観点から原則的に本人のみが確認できる仕様となっておりますが、企業側では個人情報を含まないような統計処理の上で再集計されたデータが確認できるため、プレゼンティーズム発生の恐れにつながる健康状態や心理的負荷の状態を、組織の変化としてタイムリーにとらえることができます。さらに管理者向けオプション機能として、AIが組織単位のデータを解析し、組織改善のためのアドバイスをMicrosoft Teams上で通知する機能もご用意。管理者はAIにチャット形式で施策の相談が可能で、改善方針をタイムリーに検討することができます。
健康経営の実現に向けた施策の決定や実施効果などが簡単に確認できる「健康経営®支援サービス」は、健康経営を目指す中堅・中小企業の皆さまにお勧めのサービスです。
まとめ
今回は、企業が健康経営を実現する上で重要な指標となる「プレゼンティーズム」について解説しました。健康上の理由で欠勤が続く「アブセンティーズム」に比べ、プレゼンティーズムは把握が難しい指標ですが、経済産業省の統計によれば企業の生産性喪失コスト全体の約8割を占めています。
今回はプレゼンティーズムを可視化する測定方法として、WHO-HPQ、SPQ東大1項目版、QQmethod、WLQ、WFunを紹介しました。プレゼンティーズムの解消には、まずプレゼンティーズムの現状を適切に把握した上で、具体的な損失額を求め、現状に合わせた健康経営施策を検討・実施する必要があります。また、継続的にPDCAサイクルを回して施策を評価・改善する必要もあります。
今後の働き方改革や労働力不足に対応するため、企業にとってプレゼンティーズムへの対応は必要不可欠となりつつあります。今回のコラムを参考に、自社で必要な対策について検討してみてはいかがでしょうか。
※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
※Microsoftは、米国 Microsoft Corporation およびその関連会社の商標です。
※ICT Digital Columnに記載された情報は、リリース時点のものです。
商品・サービスの内容、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。