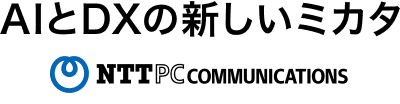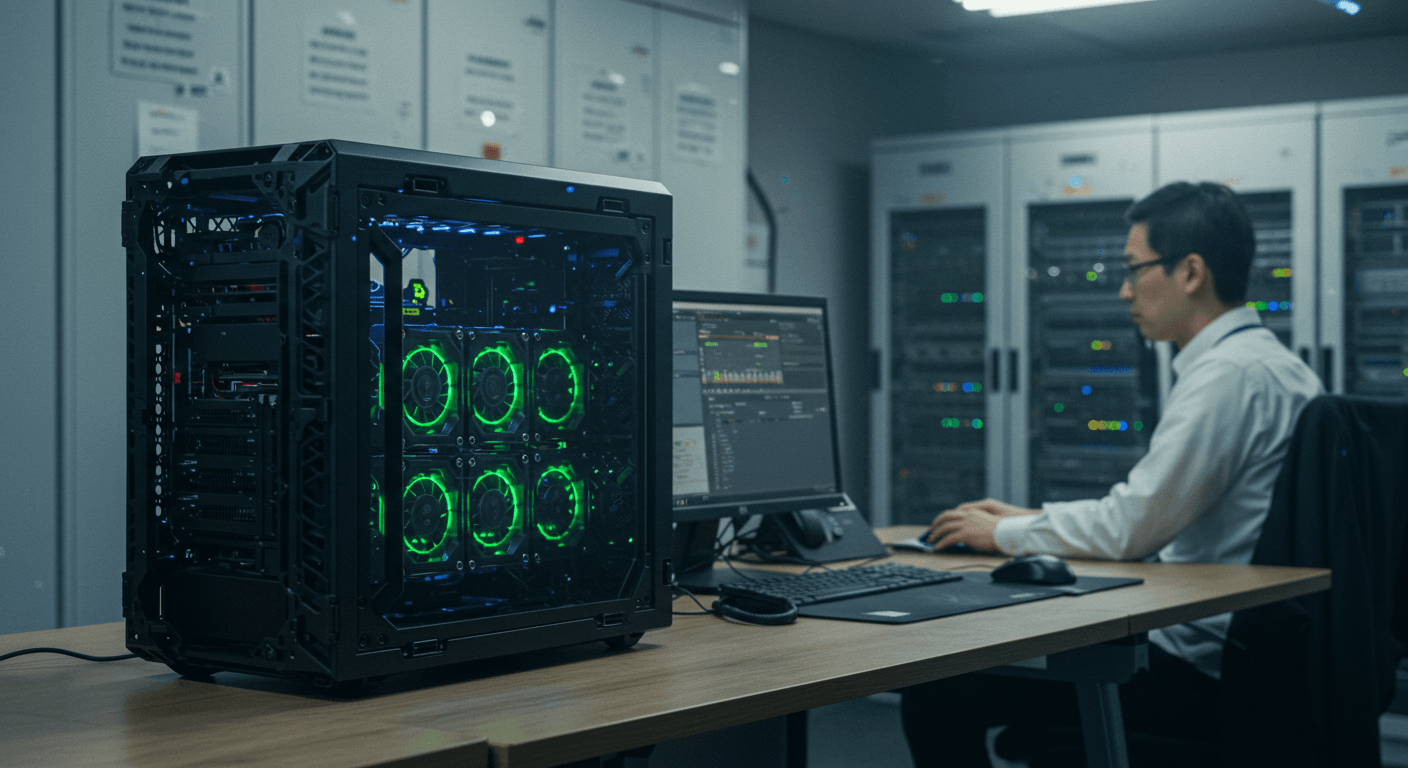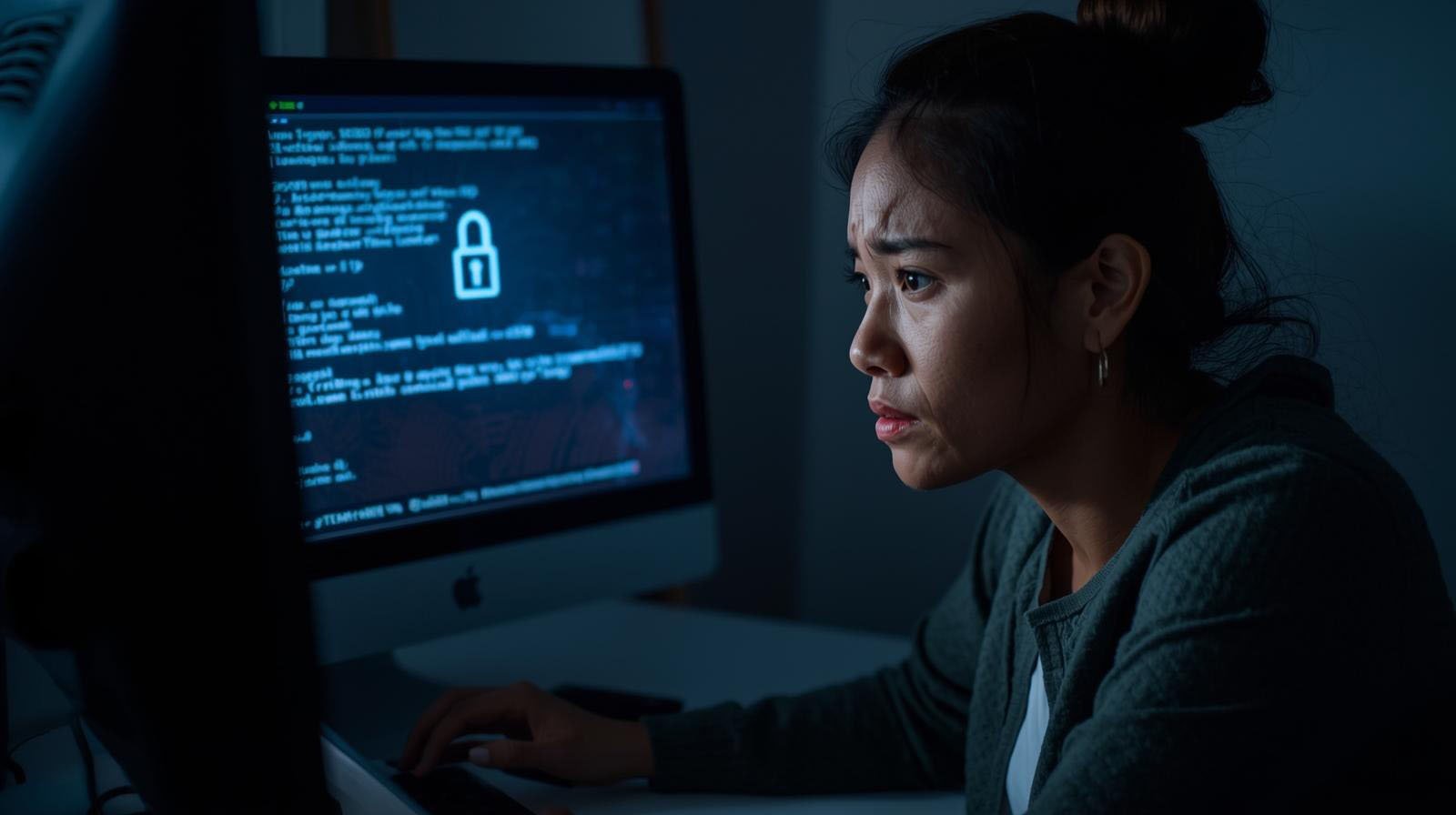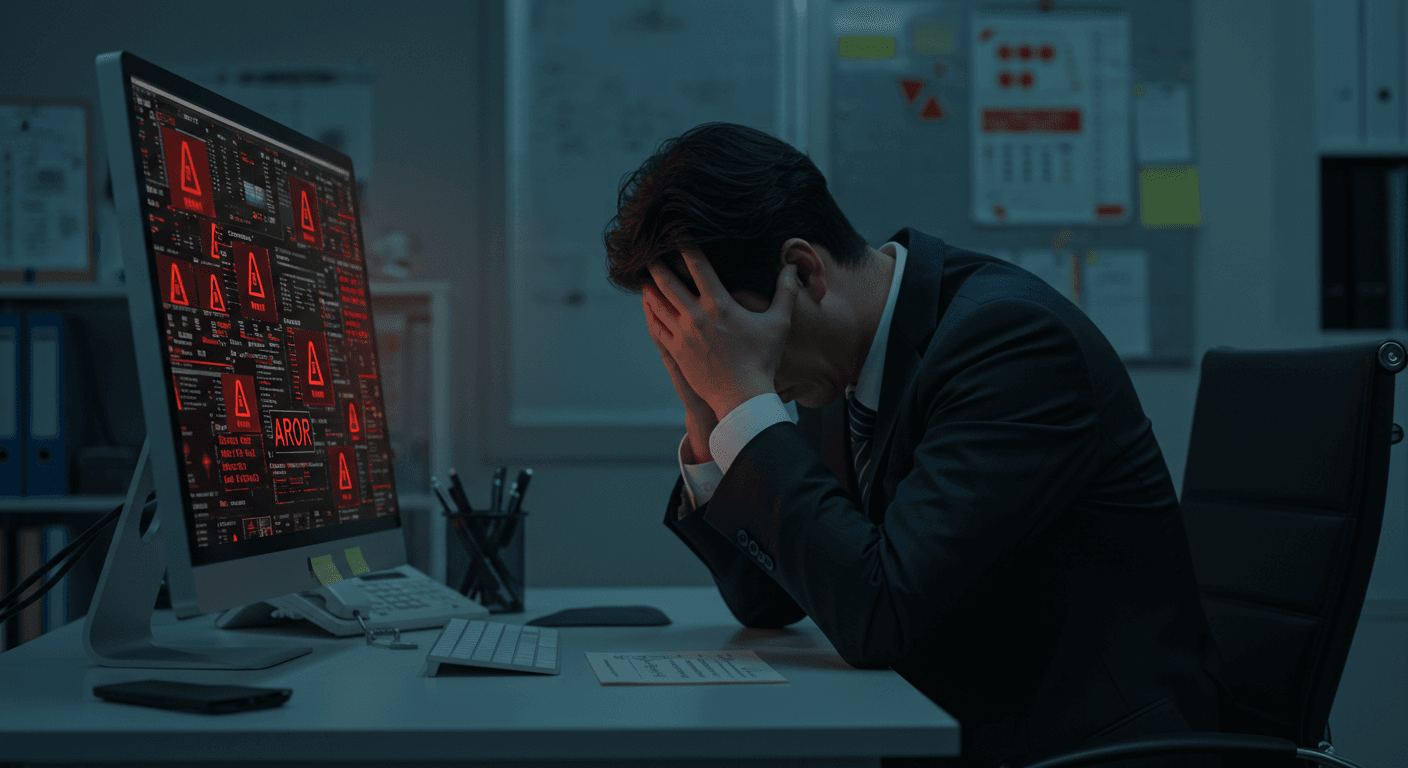「AIを使うかどうか」ではなく、「AIを前提にどう変わるか」が問われる時代に――。
ChatGPTの登場をきっかけに、多くの企業が生成AIの活用を模索し始めました。しかし、業務の一部にAIを“当てはめる”だけでは、思うような成果が出ない。そんな壁に直面している方も多いのではないでしょうか。
今、求められているのは、AIを単なるツールとして捉えるのではなく、組織・人・プロセス・インフラまでもAIを前提に再設計する発想=「AX(AIトランスフォーメーション)」です。
本記事では、AXが注目される背景から、企業がどのように取り組み始めるべきか、そして今後社会にどのようなインパクトをもたらすのかについて、日本・世界の視点からご紹介します。
AX(AIトランスフォーメーション)とは?──全社変革を実現するAI起点の考え方
AXとは、「AIを軸とした企業の業務プロセスやビジネスモデルの根本的な再構築により、持続的な競争優位を築く取り組み」を指します。
近年、生成AIの急速な進化を背景に、多くの企業がAIの活用に乗り出しており、その適用範囲は多岐にわたります。たとえば、チャットボットによる問い合わせ対応の自動化や、議事録作成の効率化といった日常業務へのAIの組み込みが進み、着実に業務効率化の成果を上げつつあります。
しかし、これらはあくまで部分的な活用にとどまるケースが多く、企業全体の構造を変革するには至っていないのが実情です。
そこで今、注目されているのが「AX」です。これは、個別業務の最適化を超え、組織全体の本質的な変革を目指す包括的なAI活用のアプローチとして、多くの企業から関心を集めています。
AXとDX(デジタルトランスフォーメーション)との違い
ここで重要になるのが、これまで企業の変革を支えてきた中心的な概念である「DX(デジタルトランスフォーメーション)」との関係性です。DXとAXは、どのような点で異なるのでしょうか。
DXは、IT、クラウド、IoT、データ活用などのデジタル技術全般を活用して、業務の効率化や顧客体験の向上を目指す取り組みです。そこには当然、AIの活用も含まれており、DXとAXは必ずしも切り離された概念ではありません。むしろ、AXはDXの進化系として、AI技術に特化したより深い変革を追求するアプローチと捉えることができます。
次のように、両者の特徴をそれぞれまとめました。
| 観点 | AX(AIトランスフォーメーション) | DX(デジタルトランスフォーメーション) |
|---|---|---|
| 定義 | AIを活用して業務・サービス・ビジネスモデルを変革し、新たな価値を創出する取り組み | デジタル技術を活用して業務やビジネスモデルを抜本的に変革し、企業競争力を高める取り組み |
| 対象技術 | AI(機械学習、自然言語処理、生成AIなど) | デジタル技術全般(クラウド、IoT、ビッグデータ、AIなど) |
| 技術の範囲 | 予測分析、自動化、パーソナライズ、意思決定支援、生成AIなどAI特化型 | 幅広い技術群を活用して業務改善から新規事業創出までをカバー |
| 目的 | 業務効率化+意思決定の高度化+AIによる新たな価値創出 | 業務効率化、顧客体験向上、新規ビジネスモデルの構築など全体最適 |
| 変革の焦点 | データ駆動型の業務再設計、AIによる判断・予測の高度化 | 全社的な業務・顧客接点・ビジネス構造のデジタル化 |
| 難易度・前提条件 | 高度なデータ環境・AIリテラシー・モデル構築/運用体制が必要 | 全社レベルでの戦略と組織改革が求められ、部門横断的な導入が必要 |
| 活用例 | AIによる需要予測と在庫最適化、AIチャットボットによるサポート自動化、AIエージェントによる業務フローの改革など | クラウド活用による業務の柔軟化、IoTデバイスを用いた稼働監視、データドリブンな意思決定の実現など |
このように、AXはAIを中核に据えた変革であり、業務の一部を効率化するにとどまらず、組織やビジネスのあり方そのものを再設計していく視点が重視されます。一方で、DXはAIも含めた包括的な概念といえるでしょう。すなわち、AXがあるからDXが不要になるというような対立関係にある言葉ではなく、相互に補完し合う関係性にあることを理解することが重要です。
なぜ今、AXなのか? ― ChatGPTの登場で潮目が変わった、企業のAI活用フェーズ
このような背景を踏まえて、なぜ今、企業がAXに注目するようになったのでしょうか。
近年、企業がAXに注目する理由として、次のような変化が挙げられます。
• 生成AIの進化:ChatGPTやClaudeなどの大規模言語モデル(LLM)の登場により、従来では難しかった高度な業務支援や対話自動化が可能となり、業務効率や顧客対応の質が飛躍的に向上する可能性が現実味を帯びてきました。
• AI活用の実用フェーズへの移行:多くの企業では、PoC(概念実証)段階を超え、実務レベルで定着しつつあるユースケースが増えています。たとえば、自動要約やFAQ対応チャットボット、議事録の自動生成、AI駆動開発など、AIの現実的な導入や生成AIの活用が、企業変革の有効な手段として利用され始めています。
• GPUの進化によるAI処理の加速と現場展開:NVIDIAなどによるGPU技術の進歩により、大規模なAIモデルも従来より短時間で処理可能になりました。これにより、PC上の試行にとどまらず、製造現場や店舗などのエッジ環境でもAIがリアルタイムに動作できるようになり、現場業務へのAI実装が現実的な選択肢となっています。
このような流れの中で、単なるIT導入や業務効率化ではなく、「AIを軸とした全社的な変革」という視点が、企業の成長戦略において急速に重要性を増しているのです。

世界はすでに動き出している ― 国内外の調査で見る、傍観者ではいられない「AI導入格差」の現実
AXへの注目が高まる中、AIの導入が企業や地域の競争力を左右する「分岐点」に差し掛かっていることを示す調査報告が、国内外で相次いでいます。
2024年以降に発表された主要レポートでは、一部の先行企業・先進地域が成果を上げる一方、多くの企業や地方がPoC(概念実証)段階にとどまり、導入格差が急速に拡大しているという実情が浮き彫りになっています。
以下に、そうした調査の中でも特に注目すべき3つのレポートを紹介します。
| 発行元 | レポート名/公開年 | 関連するポイント(一部抜粋) |
| 独立行政法人情報処理推進機構 |
17ページより引用 |
企業における AI の導入状況について尋ねた結果を示す(図表 2-5)。日本の「導入している」 の回答割合は 19.2%であり、2022 年度水準とあまり変わらず、同 40.4%である米国とは、依然 として乖離が大きい。しかし、日本の「導入している」「現在実証実験を行っている」の回答割合 の合計は2021 年度から年々増加しており、AI 技術の導入に向けた取組は緩やかではあるが拡大 しているように見受けられる |
| 公正取引委員会 |
『生成AIに関する実態調査報告書ver.1.0』(2025年) 42ページより引用 |
日本における生成 AI の市場規模は、足下では、1188 億円(2023 年)であり、市場自体は黎明期に当たるといえるが、今後、年平均で 47.2%増と急速に 成長し、2030 年には1兆 7774 億円に達する見込みであるとされ、市場は更に拡大・成長していくものと考えられる。 |
| 世界経済フォーラム(WEF)+Accentur |
25ページより引用 |
The AI revolution is not just about powerful new technology and increasing productivity – it represents a fundamental organizational transformation and rethinking around value. (日本語訳) AI革命は、単なる強力な新技術や生産性向上にとどまるものではなく、価値の再考と組織全体の根本的な変革を意味します。 |
こうした動きを見れば明らかなように、AXはもはや企業にとって“選択肢”ではなく、“生存条件”になりつつあります。
先行企業は、AIによる業務効率化や新たな価値創出に加え、市場での主導権やデータ優位性を確立しつつあり、後発組との間には埋めがたい格差が生まれ始めています。
AXは「未来への投資」ではなく、「今すぐ取り組むべき必須のテーマ」であり、まさに喫緊の経営課題といえるでしょう。
AX成功のポイントとは?──技術導入だけで終わらせないために

では、AXを単なる生成AIツールの導入で終わらせず、組織として持続的な価値創出へとつなげていくためには、どのようなポイントを意識すると良いのでしょうか。
成功には、技術・組織・業務・インフラ・人材といった多面的な視点からの設計が欠かせません。特に、PoC(概念実証)で止まるのではなく、社内に定着・展開していく“仕組み化”こそが、成功の鍵を握ります。
ここでは、AXを実現するために押さえるべき7つの重要な観点を整理してご紹介します。
【AXを成功に導く「7つの原則」】 技術導入だけで終わらせないための、組織・業務・インフラ設計
1. 業務課題から始める
「生成AIをどう使うか」ではなく、「どの課題を解決するか」から着手する。業務上の具体的な目的を起点にすることで、現場とのズレを防ぎ、導入の意味が明確になる。
2. AIを前提に業務フローを見直す
既存業務にAIを“部分適用”するだけでは効果は限定的。AIを前提としたプロセス設計へ切り替えることで、業務全体の再設計が可能になる。
3. 情報構造とデータの整備
文書の構造化、メタデータの付与、語彙の統一など、AIが「意味を理解できる」情報設計が不可欠。属人的な文書や未整理のデータでは効果を最大化できない。
4. 全社的な推進体制を築く
IT部門やAIチームだけに任せるのではなく、経営・業務・現場が一体となった体制で取り組む必要がある。現場の納得感と経営のコミットが両立して初めて変革は動く。
5. スモールスタートと横展開の仕組み化
成果の出やすい領域でPoCを始め、再現性のあるナレッジと仕組みに変換する。他部門や全社に無理なく展開できるよう、展開プロセスも設計段階で想定する。
6. 継続運用を見据えた基盤づくり
RAGや生成AIなど高負荷処理を支えるインフラ、GPUリソース、セキュリティ、ログ設計など、運用視点での“裏側の整備”が、長期活用の成否を分ける。
7. 倫理とリスクに向き合うガバナンス
誤出力・データリーク・バイアスなど、生成AI固有のリスクをどう管理するか。ルールづくりやモニタリング体制を最初から設計することで、社内展開の信頼性が高まる。
このように、AXの本質は「AIを導入すること」そのものではなく、AIを業務や組織の前提として捉え、継続的に活用できる仕組みを整えることにあります。 その実現には、現場の業務設計やデータ整備に加えて、AI活用を安定的に支える実行基盤の整備も欠かせません。とくに文章や画像・動画生成AIの活用や大規模の社内データ処理のような高負荷処理が常態化する環境では、GPUを活用した社内インフラが、その基盤として重要な役割を果たすでしょう。
今後AXは社会にどのような変化をもたらすか?
これまで見てきたとおり、企業の内部でAIの活用が進むだけでなく、それを基盤とした意思決定・事業運営・価値創出のあり方そのものが変わり始めています。 今後、AXは社会全体に対してどのような変化をもたらすのでしょうか。
ここでは、これまでの文脈を踏まえつつ、以下の4つの観点からそのインパクトを整理してみましょう。
1.競争ルールの変化:勝敗を分ける「AIケイパビリティ」
AIを組織全体に組み込んだ企業は、業務のスピード・正確性・創造性のすべてにおいて飛躍的なパフォーマンス向上を実現します。 結果として、「AIを前提に動ける企業」と「従来のやり方に留まる企業」とで、競争格差が大きく広がることが予想されます。
また、AIを活用した新しいビジネスモデル(例:AIによる顧客提案、自動化された研究開発、パーソナライズサービス)を早期に構築した企業が、新市場を牽引していく構図が形成されつつあります。
2.人材価値の再定義:「AIを使いこなす」から「AIと協働する」へ
AXによって、定型業務の多くはAIによって代替される一方、人間には“判断・共創・感性”といった領域がより強く求められるようになります。 これにより、企業は従業員に対して「タスクをこなす力」ではなく、“AIと協働する力”や“問いを立てる力”を重視するようになっていきます。
同時に、AIリテラシーは全職種において必須スキルとなり、経理や営業、製造などあらゆる職域で再教育が必要となるでしょう。
3.産業構造の転換:バリューチェーンの再構築
AXの進展により、従来の業界構造も再編されていきます。 たとえば、製造業では品質管理や設計プロセスがAIによって高速化・最適化され、金融業ではAIによるリスク分析・契約審査が主流となるなど、各産業のバリューチェーンそのものが変化します。
また、AXに取り組む企業・地域と、そうでない地域との間で“デジタル格差”が再び拡大することも懸念されています。今後は地方自治体や中堅企業においても、AIインフラ・教育・データ活用基盤への投資が不可避となります。
4. 社会制度の見直し:問われる「AIの説明責任と倫理」
AIが社会のあらゆる判断・創造に関わるようになるにつれ、説明責任・透明性・倫理性といった価値基準がより強く問われるようになります。 特に、公共性の高い領域(行政・医療・教育など)では、「人が判断し、AIが支える」構図の再設計が求められるでしょう。
AXを推進するうえで、今後は企業任せにしない社会全体のガバナンスやルール整備が不可欠になります。たとえば、AIに関する説明責任、バイアス管理、プライバシー保護などの制度設計が進められると考えられます。
▶︎関連記事:社会を支えるAI×GPU|医療・教育・防災・交通にどう活かすか
https://www.nttpc.co.jp/focusinsight/topic/topic10_aixgpu/
まとめ
本記事では、国内外で加速するAXの潮流を踏まえ、なぜ今このテーマが企業にとって重要なのか、成功企業とそうでない企業の違い、そしてAXを単なる技術導入で終わらせず、組織変革へと昇華させるために押さえるべき視点についてご紹介しました。
AXは、AIを導入すること自体が目的ではなく、それを自社にどう根づかせ、継続的な価値創出へとつなげるかが問われる取り組みです。AIが前提となる時代において、企業の変革は“選択”ではなく“条件”へと変わりつつあります。
こうした大きな変革を実現するには、大規模なAIの活用が不可欠です。そして、そのAIを動作させるためには高性能なGPUが必要となります。
NTTPCはNVIDIA認定エリートパートナーとして、生成AI/LLM向けGPUクラスタの設計・構築から運用インフラの整備までトータルで支援が可能です。
さらに、NTTPCでは、高品質な閉域ネットワークにAIを組み込み、運用業務を自動化する企業向けネットワーク(VPN)&セキュリティサービス「Prime ConnectONE®」を提供しています。AXを前提としたネットワーク導入を検討されている方は、ぜひご活用ください。
AXの実装に向けた第一歩として、GPUの導入を検討されている方や、AXに適した閉域ネットワークサービスをお探しの方は、お気軽にご相談ください。
※ChatGPTは、OpenAI社の商標または登録商標です。
※ClaudeはAnthropic, PBCの商標です。
※NVIDIAは、米国および他国のNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。