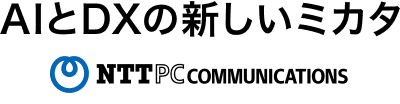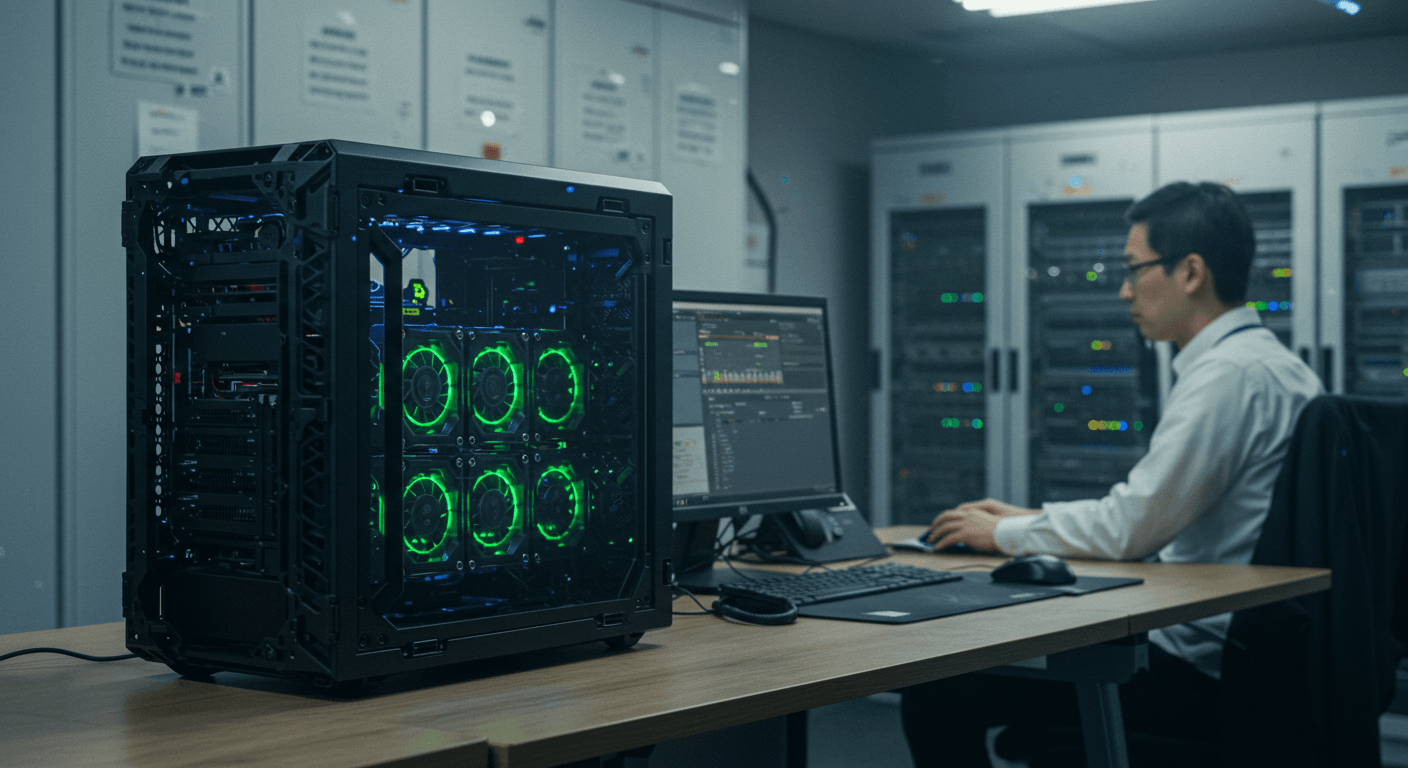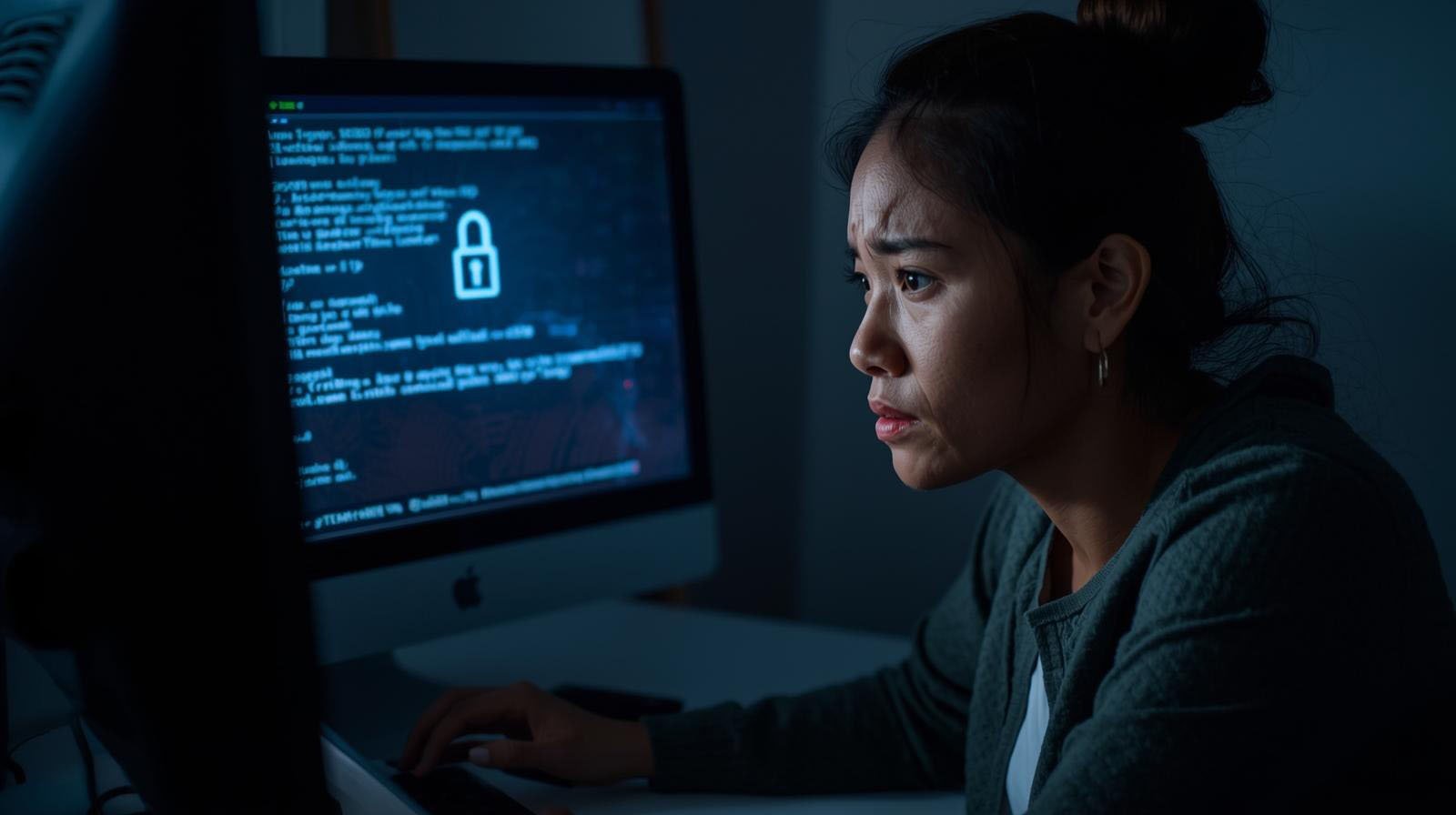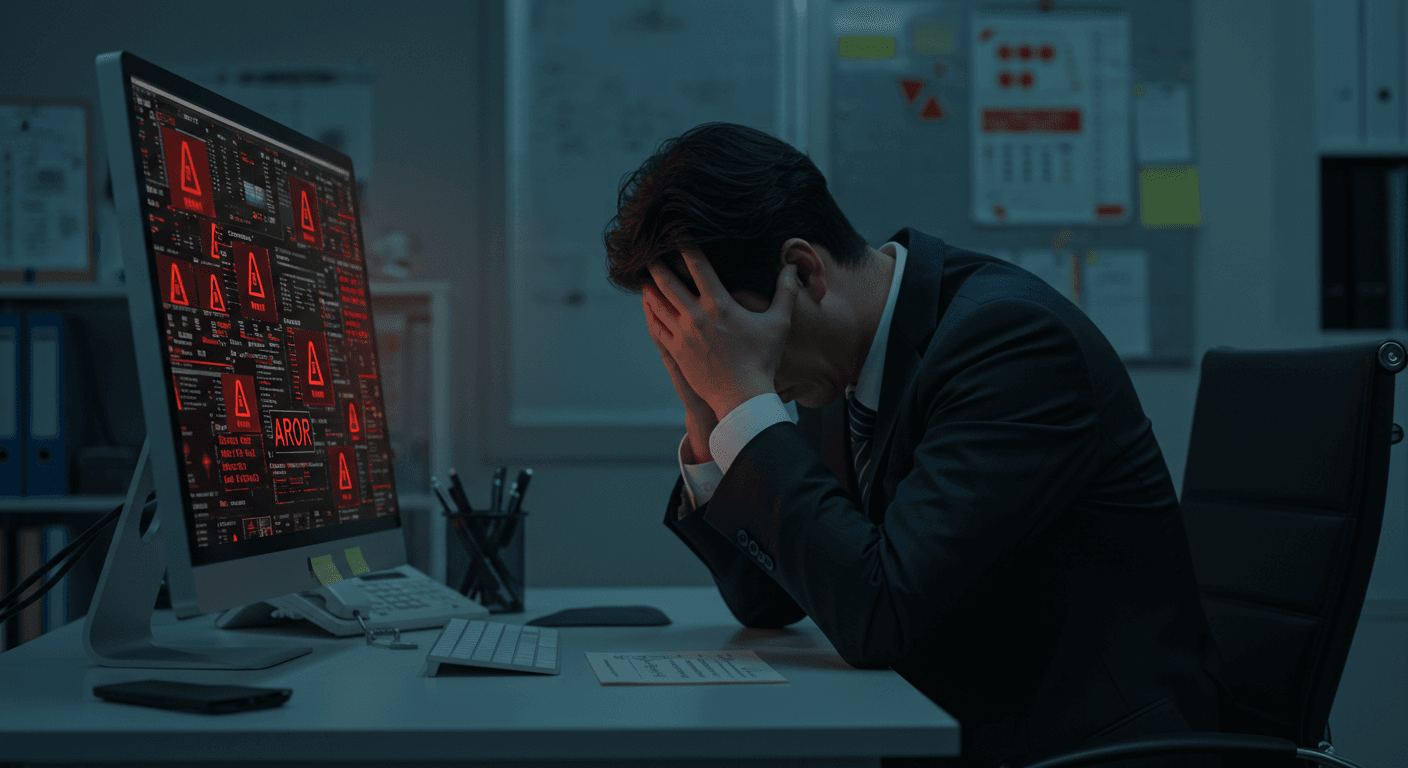2025年6月、労働安全衛生規則の改正により、職場での熱中症対策が罰則付きで義務化されました。詳細は、[厚生労働省 富山労働局の解説ページ](HTML形式)および [厚生労働省公式PDF資料はこちら] をご参照ください。毎年のように記録的な猛暑が続き、建設現場や工場、倉庫などで働く人の熱中症リスクは年々高まっています。「うちの現場は大丈夫」と思っていても、適切な対策を怠れば、法的な罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。
これまでのように管理者の巡回や作業員本人の申告に頼る方法では、異常の早期発見が難しく、重篤化のリスクが高まります。
そこで注目されているのが、作業者の体調変化を第三者的に把握し、初動対応につなげる「見守り」の考え方です。
本記事では、法令内容の要点を整理したうえで、企業が現場で何を判断し、どこまで対応すべきかという視点から、実効性のある熱中症対策の考え方を整理します。
熱中症対策義務化の対象は?必要な対策や罰則の要点を整理
労働安全衛生規則の改正により、2025年6月から職場の熱中症対策が義務化されました。
ただし、対象はすべての企業ではなく、一定の条件を満たす作業を実施する企業において法的義務となります。
違反した場合は罰則があり、企業にはこれまで以上に計画的な熱中症対策が求められています。
労働安全衛生規則の改正により、2025年6月から職場の熱中症対策が義務化されました。ただし、対象はすべての企業ではなく、一定の条件を満たす作業を実施する企業において法的義務となります。違反した場合は罰則があり、企業にはこれまで以上に計画的な熱中症対策が求められています。
■熱中症対策義務化の対象・対策・罰則
| 対象 | WBGT(暑さ指数)28以上または気温31℃以上の環境で、連続して1時間以上または1日4時間を超える作業が見込まれる企業 |
|---|---|
| 対策 | (1)報告体制の整備 (2)実施手順の作成 (3)関係者への周知 |
| 罰則 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
熱中症対策が義務付けられる対象
2025年6月からの熱中症対策の義務化について、職種や業種の指定はありません。近年、東京都では7月上旬から9月中旬にかけてほぼ連日WBGT28以上を観測しており、夏場に屋外で連続して1時間以上または1日4時間以上作業する企業は、基本的に熱中症対策義務化の対象になるといえます。
<熱中症対策義務化の対象となる主な作業場>
- 建設現場(屋外作業・仮設建屋・トンネル工事)
- 製造業の高温作業エリア(鋳造・溶接・炉前作業)
- 閉域網とインターネットの併用によるコスト削減
- 倉庫・物流現場(荷役・搬送作業)
- 警備員(交通誘導・警備業務)
企業に義務付けられる熱中症対策の内容
2025年6月から義務化となった熱中症対策は次の3つです。対策を怠った企業には法的な罰則が科せられるので、確実に対応する必要があります。
以下は、労働安全衛生規則に基づき企業に求められる最低限の対応です。ただし、作業環境や業務内容によっては、これらの対応だけでは体調異常の早期発見が難しい場合があります。
-
作業者が分散して働いており、管理者が常時巡回できない
-
一人作業や少人数作業が多く、異変に気づく第三者が近くにいない
-
体調変化の把握が、本人からの申告に依存している
-
実施手順は定めているが、実際の現場では形骸化している
このような場合、「報告を待つ前に気づく仕組み」や「初動を自動的に促す仕組み」まで含めて検討する必要があります。
■企業が対応すべき3つの熱中症対策
| 報告体制の整備 | 熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、それを報告するための体制(連絡先や担当者)を作業場ごとに整備する |
|---|---|
| 実施手順の作成 | 症状の悪化を防止するために必要な措置(身体冷却、医療機関への搬送など)の実施手順を事業場ごとに作成する |
| 関係者への周知 | 報告体制や実施手順を関係者に周知する |
これらはあくまで制度上求められている基本事項であり、現場の作業環境や人員配置によっては、これだけでは十分とは言えないケースもあります。
特に、作業員が分散して働く現場や、一人作業が発生する環境では、「異変にどう気づくか」という点が運用上の課題になりやすくなります。
報告待ちでは守れない!従来の熱中症対策の限界
過去の熱中症による死亡災害を分析すると、発見の遅れによる重篤化や、医療機関に搬送しないといった対応の不備が主な要因として挙げられています。職場の熱中症は、早期に発見し、すぐに医療機関に搬送するという、適切な対処が重要です。
熱中症リスクの高い屋外作業場がある企業をはじめ、多くの企業では、これまでも熱中症対策を実施しています。しかし、従来の対策だけでは限界があることも見えてきました。
従来の熱中症対策としては、作業前の健康確認や休憩所の設置、水分補給の促進といった基本的な取り組みが広く行われています。しかしこれらは、発生した熱中症の兆候を能動的に把握したり、初期段階での対応につなげたりする仕組みとしては十分ではありません。
<従来の熱中症対策例>
- 作業前点呼による作業員の健康確認
- 水分や塩分補給の推奨と提供
- 体の冷却(ファン、保冷剤など)
- 休憩所の設置
- 作業場の巡視
法令対応や注意喚起を行っていても、実際の現場では体調異変を早期に察知することが難しいケースがあります。特に、人の判断や申告を前提とした運用では、異常に気づくタイミングが遅れやすく、結果として対応が後手に回るリスクが残ります。
熱中症の初期症状は頭痛や倦怠感など、ほかの体調不良と似ているため、自分で判断するのが難しく、多少の無理をしてしまいがちです。その結果、体調不良の自己申告が遅れ、対応が後手に回ることが少なくありません。また、巡視だけで作業員の状態を把握するには限界があります。
2025年6月に施行された義務化の内容には含まれていませんが、厚生労働省はウェアラブル端末を使った熱中症見守りサービスなど、作業員の状態を企業が能動的に把握する仕組みの導入を推奨しています。
導入検討が増えている「熱中症見守りサービス」に注目

熱中症の初期症状は判断が難しく、従来の熱中症対策では早期発見のハードルが高いといえます。そこで注目を集めているのが、第三者的にシステムで危険を検知できる仕組みです。
近年、様々な熱中症見守りサービスが提供されており、現場環境や予算に応じて選択できるようになっています。
セルフケア用のウェアラブルデバイス
セルフケア用のウェアラブルデバイスは、作業員個人が自身の体調を確認できるタイプの見守りツールです。腕時計型や胸部装着型のデバイスが一般的で、心拍数や体温、活動量などを測定し、異常を検知すると本人にアラートを通知します。
自分の体調を客観的に把握できるメリットがある一方で、本人への通知にとどまるため、意識を失った場合や通知を無視した場合には対応が遅れる可能性もあります。
ウェアラブル+クラウドで異常を通知するIoT型見守りサービス
IoT型見守りサービスは、作業員が装着したウェアラブル端末から取得したデータをクラウドで分析し、異常を検知した際に管理者に即座に通知するシステムです。心拍数、体温、活動量、位置情報などを確認できるので、熱中症の兆候の早期発見が期待できます。
最大のメリットは、作業員本人の自覚や申告に頼らず、第三者的な視点で客観的に体調変化を捉えられることです。管理者は複数の作業者の状況を一元的に把握でき、異常発生時に対応することで、日々の運用の手間も削減されます。
また、過去のデータを蓄積・分析することで、個人の体調パターンを把握できるので、より精度の高い熱中症対策が可能となります。
監視カメラによる常時モニタリング
監視カメラによるモニタリングは、作業現場に設置したカメラで作業員の様子を常時監視し、異常行動や倒れている状況を検知する方法です。AI技術を活用して人の動きを解析し、異常行動を自動検知する機能を持つサービスもあります。
カメラの死角が生じやすい点や、広範囲の現場をカバーするには多数のカメラが必要になり、コストが高くなる点はデメリットです。
ウェアラブルIoTサービス「みまもりがじゅ丸®」
NTTPCの「みまもりがじゅ丸®」は、作業員の「脈拍」や「位置情報」を専用のウェアラブル端末で取得し、体調の変化をリアルタイムで伝えます。作業員の安全と健康管理を強化し、異変情報を継続的に確認・分析することで、「いつも」の状態を見守ります。
<みまもりがじゅ丸®の機能>
- 脈拍(脈拍上限値・下限値超えの検知)
- 熱ストレス(熱中症のおそれの検知)
- 作業継続度(体への負荷の可視化)
- 転倒検知(加速度情報からの転倒検知)
- SOS通知機能
計測データは常時クラウドに送信・蓄積され、管理者はダッシュボード上で体調状況をリアルタイムに確認することが可能です。併せて、異常値検知時にはアラート通知により迅速な初期対応が行えます。これにより、自覚や申告に頼らず早期発見につながるでしょう。
熱中症見守りサービス選びのポイントは?導入時のよくある課題と対応策
熱中症見守りサービスの導入を検討する際、多くの企業が直面する課題があります。ここでは、サービス選びのポイントとともに、導入時のよくある課題と対応策を見ていきましょう。
コスト・費用対効果の懸念
熱中症見守りサービスの初期費用やランニングコストは、提供するサービスによって様々です。そのため、サービスを選定する際には、導入費用と運用コストをしっかり確認することが重要です。
導入を検討する際、経営層から「費用対効果は見合っているのか?」と指摘されることも少なくありません。その際には、熱中症対策の強化によって得られる効果を、できるだけ具体的・定量的に伝えることがポイントです。
例えば、次のような効果を数字で示すと、経営層の理解を得やすくなります。
<熱中症見守りサービスの効果>
- 労働災害による損失の削減
- 作業効率の向上
- 作業員の健康維持による長期的な生産性の向上
また、万が一熱中症による労働災害が発生した場合のリスク(治療費、休業補償、法的責任、企業イメージの低下など)と比較し、サービス導入の妥当性を示すことも効果的です。
運用や作業員への教育の負荷
現場の安全管理部門からは、熱中症見守りサービスの導入によって「運用の手間が増えるのではないか」「作業員への教育が負担になるのでは」といった懸念が挙がることがあります。新しいシステムを導入することで、かえって現場の負担が増えるのではという心配です。
このような課題に対しては、専門知識がなくても運用できるシンプルなサービスかどうかを、事前に確認することが大切です。多くのサービスは自動でデータを計測・送信する仕組みとなっており、管理者の負担は最小限に抑えられています。
また、複雑な設定などはなく、見守り対象者がウェアラブル端末を身に着けるだけで使用可能です。
さらに、これまで必要だった巡視の頻度を減らせるなど、従来の安全対策にかかっていた人的リソースの削減につながる点を伝えることで、現場の理解や納得を得やすくなります。
現場からの「監視では?」という不信感
熱中症見守りサービスを導入する際、現場の作業員が「監視されている」と感じ、不信感や心理的な負担につながるケースがあります。安全のための取り組みであっても、プライバシーへの不安から反発が起きることは珍しくありません。
このような懸念に対しては、管理側が取得する情報の範囲を明確に開示し、「あくまで従業員の安全を守るための見守りである」ことを丁寧に説明することが大切です。どのようなデータが取得されるのか、実際の管理画面を見せながら説明するなど、情報を可視化することで現場の理解を得やすくなります。
また、位置情報の取得を任意で設定できるといったプライバシーに配慮した機能を備えたサービスを選ぶことで、心理的なハードルを下げることも可能です。
熱中症対策の義務化に合わせて対策を強化

2025年6月から、一定条件下の職場における熱中症対策が罰則付きで義務化されました。猛暑が続く中、従来の対策だけではリスクを十分に防ぎきれない現実があり、企業にはより確実で効果的な熱中症対策の導入が求められています。
中でも注目されているのが、作業員の状態をリアルタイムで把握できる熱中症見守りサービスです。本人の自覚に頼らず体調の異常を検知できる仕組みは、熱中症の早期対応が期待でき、作業現場の安全性を高めます。
義務化を機に企業の熱中症対策は、「最低限の対処」から「戦略的な安全管理」へと変わりつつあります。自社に合った対策を見直し、安心・安全な職場環境づくりを進めていきましょう。