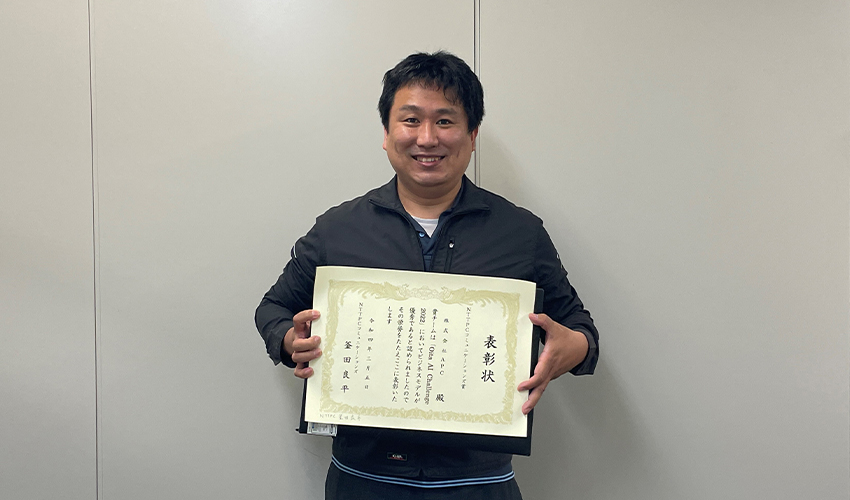INTERVIEWインタビュー
【Vol.21】【Oita AI Challenge 2022受賞企業】 災害時の活用が期待される「ジェスチャーAI」。先端技術の実用化を目指すAPCの想いとは。
大分県公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所と「おおいたAIテクノロジーセンター(OAITC)」の主催により行われたビジネスコンテスト「Oita AI Challenge 2022」が、2022年3月5日に開催されました。株式会社APCが発表した「ドローン自律航行のためのラスト100フィートAI~災害時にも対応した完全自律配送の実現に向けて~」と題したプレゼンテーションが、NTTPCコミュニケーションズ賞を受賞。本プレゼンでAPCが伝えたかった想いとはなにか。受賞後に、同社情報システム事業部 大分開発センター長 後藤喜博さんにお話を伺いました。

航空機認識の実証実験を通じて雑談の中から生まれたアイデア
- 浅井
-
まずAPCの事業内容を教えてください。
- 後藤
-
株式会社APC 情報システム事業部 大分開発センター長 後藤喜博(以下、後藤) 主に情報システム事業と半導体事業を行っています。私が所属している情報システム事業では、人の眼を機械の目に置き換え、認識判断する目視の自動化ソリューション「現場のAI」と、熟練の精緻な技をデジタル化する技の数値化ソリューション「匠のAI」を展開しています。半導体事業は、米国Lam Research社製の半導体製造装置のインスタレーションと装置・部品の修理・改造を行っております。
情報システム事業全体としては、コンピュータービジョンとFAソフトウェアを核としたカテゴリーの開発を行っており、それらの相乗効果によりソフトウェアやプロダクトを提供しています。
FAソフトウェア開発はハードウェア関連技術をもとに、お客さま環境など現場ノウハウなども合わせた上で、エンドユーザーに近いところで実施されています。コンピュータービジョン開発は、論理ベースでバーチャル空間を活用して実施されることが多くなっています。FAソフトウェアとコンピュータービジョン、これらの2つの要素を結びつけるノウハウこそが弊社のコアコンピタンスだと考えています。
- 浅井
-
今回のプレゼンにある、ドローンを活用したラスト100フィートへの配送をAIでやろうと考えられたきっかけはなんですか。
- 後藤
-
当社は航空機自動認識を目的とした実証実験を2021年10月から実施しております。
航空機も同様、基本的に「空の世界」は自動化が進んでいます。ただし、離陸と着陸時は自動運転ではなく、手動で行われることがほとんどです。気候条件などを勘案すると自動運転の方がより安全かもしれませんが、離着陸時の運転モード切替えには、航空機側や滑走路側などに様々な設備が必要だと聞いています。
もちろん、機長の運転感覚を保持するという目的もあるとは思いますが、離着陸時には細かな操作・確認等が必要であり、状況判断が重要であるということだと思われます。
ドローンにおける配送も登録地点に到着すること自体は問題ないですが、登録地点に着陸する・物を投下するといった場合には、周辺の状況を確認し、真下に人や物などの障害物はないかなど、安全性が重要となります。結果、遠隔でのモニタリング映像を人が確認し、判断を下しているというのが現状ではないでしょうか。
そこで当社は、ラスト100フィートを自律走行できる状況判断可能なAIを作ろうということになりました。大分県がドローンの活用を推進していることも理由の1つです。
- 浅井
-
ドローンで配送をするときの受け渡しに課題を感じられたとか。
- 後藤
-
先ほどの話と前後し、申し訳ありませんが、ある時、ドローンでの課題についてオフィスでメンバーと雑談してるとき、「ドローンで配送はできても、受け渡しは難しいんじゃないの?」という話になったのです。そこで調べたところ、ドローン配送の実証実験では、「どこどこからスタートした」「何キロ飛んだ」という結果は公表していても、受け渡しのことに触れているものはありませんでした。
また、ドローン配送が進んでいるアメリカでは広い土地があるので、受け渡しというよりも、配送物をただ落としているだけなんですよ。そこで、受け渡しの部分に目を向けてみてはどうかと考えたのです。

国ごとで異なる「ジェスチャー」。AIモデル実現へ挑戦したい
- 浅井
-
ドローン配送の最後の受け渡し部分は世界でも進んでいないのですね。配送物の受け渡しをAPCの技術で実現するにあたり、難しいと感じられた部分はありますか。
- 後藤
-
人が荷物を渡そうとするとき、まず眼で見て人がいるとわかったら、その人に近づいていきます。その点では弊社の画像認識技術を活用することができます。「こっちにおいで」「向こうだよ」という声の認識についても、音声認識技術は一般的にかなり浸透しており、弊社の技術力と繋ぎ合わせることで実現できるのではと考えています。
今回のプレゼンアイデアの核となる部分としては、身振り手振りなどの「ジェスチャーを認識すること」だと考えました。ただ、日本と海外では同じジェスチャーでも意味が違います。例えば、日本人がする「こっちにおいで」というジェスチャーは海外だと「あっちに行け」の意味となるようです。ジェスチャーは国ごとによって異なるため、様々な種類・パターンを学習させる必要があります。
また、その認識結果によって、正確な動作を行うための状況判断の脳となる独自のAI開発が必要となる難しさはあります。
- 浅井
-
「ラスト100フィートAI」の実現は何年ごろを目指していますか。
- 後藤
-
現時点では明言できませんが、まずは、「ジェスチャーを認識する」ということから始めていき、数年後には自律走行支援のAIを実現させたいと思っています。
- 浅井
-
ターゲットとしている業界はありますか。
- 後藤
-
プレゼンではわかりやすく配送業を例に挙げていたのですが、プレゼンタイトルに「災害にも対応した」とあるように、最大のターゲットは自治体です。ドローンが活躍できる場として、災害の一時対応が期待されていると思っています。今はドローンで監視を行い、状況を伝える際にカメラで撮影して動画や画像を送信していますが、何か判断をするときには人間が遠隔で行っています。その判断にはさまざまなルールが存在しているため、判断が遅れることもあります。
ただ災害のような緊急事態下では、ある程度決まったルールの下で判断して動き、自律的に行動していくことが求められます。そこで自律航行し自律配送できるドローンは、災害時に孤立してしまった施設や人が発生したときに活用できると思います。そう考えていくと、ドローンアイデアのメインターゲットとして自治体が挙がるわけです。

災害時に役立つオフラインで自律するドローン技術
- 浅井
-
プレゼンで伝えきれなかった想いを聞かせてください。
- 後藤
-
今回のビジネスアイデアは、電波がつながっていることが前提と捉えられた方もいるかもしれません。しかし私たちは、ドローン自体にGPUを搭載したエッジPCを積んで自律的に判断するものではないといけないと考えています。
その理由として、災害時には携帯のネットワークにつながらないことがあるからです。また、停電も想定されます。携帯電波の接続状況に左右されることなく、自律的に判断し、録画した画像は携帯電波がつながるエリアに戻ってきたときに、データを送信するというような仕組みが謳いたかった部分です。
ドローンが持つ基本的な技術である「安定して空を飛ぶ」というところにAIを組み合わせることによって、災害時にも役立つということがもっとも伝えたかったことです。
- 浅井
-
このビジネスアイデアが実現されたときには、どんな人にどういう価値を感じてもらいたいか、喜んでもらいたいかを教えてください。
- 後藤
-
本ビジネスアイデアをドローンの観点から言えば、災害救助や配送という面が強いのですが、弊社が力を入れているジェスチャーAIという観点から言うと、それとは別に活用できることもあります。例えば、世の中には、監視カメラをはじめとしてさまざまな種類のカメラが設置されています。そこで得られた情報はビッグデータとして役立てられますが、ジェスチャーAIで人命救助に活用することもできます。
一例として、プールに設置されている監視カメラに「これは人が溺れているの?それとも泳いでるの?」という状況が発生したとき、「この地点で人がこういう状態になっています」と知らせてくれるだけでも使い道があると思います。
現在の監視カメラの映像は、結局すべて事後にしか役立っていません。証拠として押さえるために動画や画像を記録しておくわけですが、リアルタイムで人が助けを求めている場面を判断して通知されるだけでも、救われるものはたくさんあるのではないかと考えています。
- 浅井
-
ジェスチャーAIの今後の可能性は。
- 後藤
-
今後の可能性としては、先ほど話をした災害や海難救助などでの活用が想定されますし、物流での配送や運搬でも活用できると思っています。
世界的に開発が急がれている自動運転分野における自転車の手信号を認識するということも可能となります。
現状のジェスチャーAIは、例えばテレビのチャンネルをジェスチャーで示して切り替えたり、手話を理解するといった、あらかじめ決められたジェスチャーが判別できるといったもので、自然言語処理でいうとまだ分かち書きされた書き言葉による文章が理解できるレベルです。コマンドとしてのジェスチャーを知らないユーザーの自然な仕草を理解することは、いわば普通の会話を理解するようなものですが、一般化できれば応用範囲は広いでしょう。
大分のAI企業として、価値あるアイデアと技術力で貢献したい
- 浅井
-
最後に、今回受賞されたビジネスアイデアを活用して、APCが大分県、ひいては日本に対して貢献していきたいことを教えてください。
- 後藤
-
日本は世界的に見ても地震大国として、災害とは切っても切り離せないものです。また、大分県や地方の方では、僻地への物資供給・搬送が高齢化・人手不足などの影響により、ますます利便性が悪くなる可能性があります。
私共としては、今回のビジネスアイデアを活用することにより、災害や海難救助の手助けとなり、また利便性の向上に貢献できると思っています。
また、当社のプロダクトである遠隔業務支援ツール「アイちゃん」を災害復旧の支援ツールとして、AIによる概念実証を手軽に行える「Chimera AI Evangelist」をSTEAM教育ツールとして提供するなど大分県全体のITリテラシー向上に取り組んでいるところです。
当社はこれからもあらゆる課題や問題を技術的な観点で解決へと導き、誰もが便利で豊かさを感じる社会の実現に向けて突き進んで参ります。