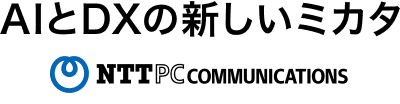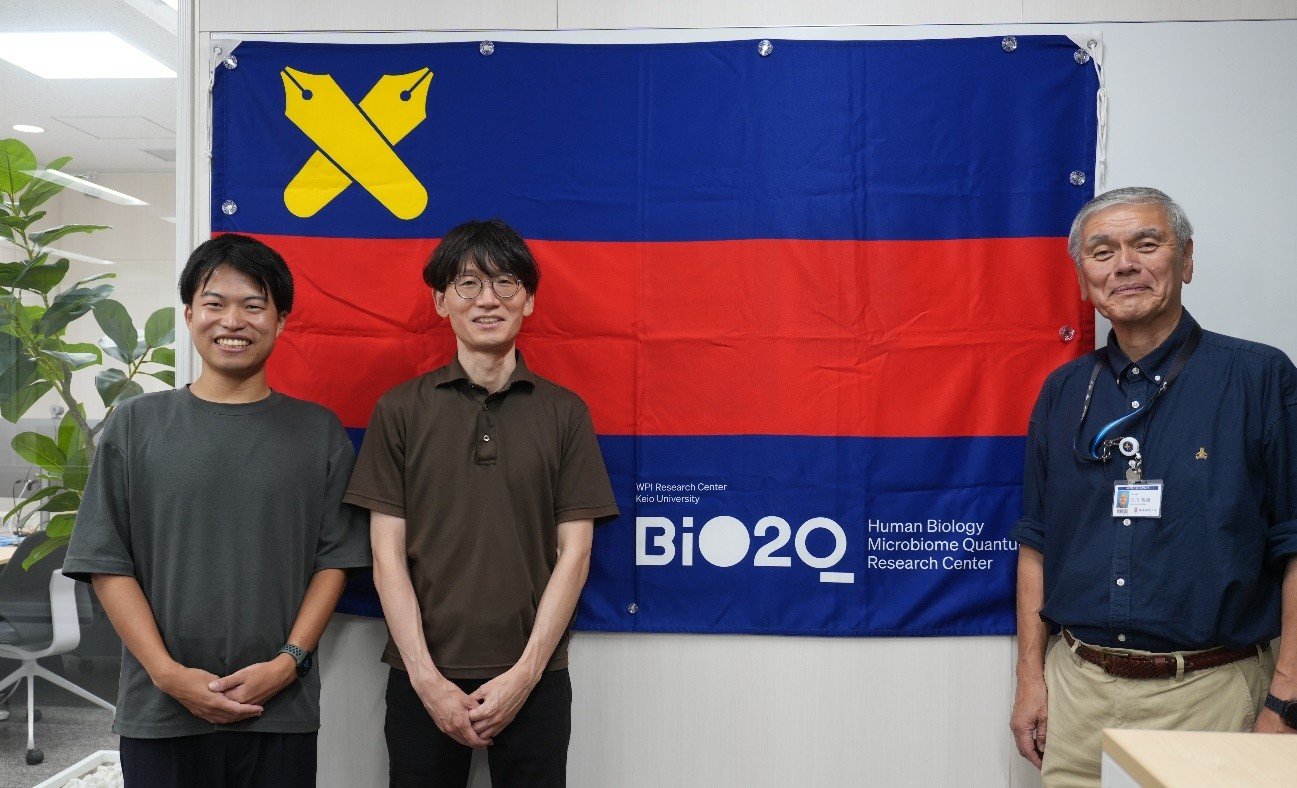NVIDIA Omniverse™が拓くサイバニクス空間と人協調型ロボティクスの未来 ~デジタルツインで実現する誰も取り残さない社会~
筑波大学サイバニクス研究センター
筑波大学未来社会工学開発研究センター
CYBERDYNE株式会社
【研究の課題】
- 生活様式の多様化に対応し、空間や時間を超えて人と人、人とロボットがインタラクションできるシステムの実現
- 物理空間とサイバー空間を双方向リアルタイムで連携させ、人が両空間を自由に行き来できる「サイバニクス空間」の構築
- 多様なロボット・IoTデバイス・センサーと連携可能で、高い拡張性を持つプラットフォームの選定
- 個人情報・秘匿情報を扱う研究のため、オンプレミス環境でセキュアに運用できるハイエンド計算基盤の確保
- 研究の成果を社会実装へと展開し、ルール整備・人材育成・経済サイクルの包括的な推進

【NVIDIA Omniverseによる実現内容】
- 人、物理空間、サイバー空間がリアルタイムで双方向連携するサイバニクス空間を構築
- ROSやUnityなど既存プラットフォームとの高い連携性により、多様なデバイス・ロボット・センサーを統合
- GPU仮想化技術により、ハイエンドでない端末でも高度な3Dレンダリングと数値計算を実現
- オンプレミス環境(DGX1、OVXレンダリングサーバー)での運用により、患者情報を含むデータのセキュアな研究開発が可能
- 導入から6〜7ヶ月で原理検証は達成、将来的にはサイバニクス産業の創出を通じた包括的メディカル・ヘルスケアへの展開を目指す
筑波大学サイバニクス研究センターでは、人・ロボット・AI・情報系を融合/複合した新しい学術領域「サイバニクス」の研究開発が進んでいる。30年近くにわたり開拓されてきた本研究センターでは、世界初の装着型サイボーグ「HAL®」をはじめ、社会の複雑な課題解決に向けた技術開発が行われてきた。
同センターの上原皓先生は、「テクノロジーで誰も取り残さない社会を実現する」というビジョンのもと、人協調型ロボット研究をはじめ、細胞培養、MRI画像解析など、基礎から実際までの幅広い研究に取り組んでいる。中でも今回は、NVIDIA Omniverse ※1 を活用して人、物理空間、サイバー空間を有機的につなぐ「サイバニクス空間(「人」+「サイバー・フィジカル空間」)」の構築に焦点を当て、インタビューを行った。高い拡張性とGPU活用による高性能処理を実現するNVIDIA Omniverseは、多様なロボットやIoTデバイスをリアルタイムで統合し、医療・福祉分野をはじめとする幅広い応用を可能にする。NVIDIA Omniverse選定の背景、実装プロセス、そして社会実装に向けた挑戦と新産業創出への展望について語っていただいた。
※1 NVIDIA Omniverse:NVIDIA社が提供する3Dシミュレーション・プラットフォーム。複数のツールやAIモデルを連携させ、現実世界の環境や動作を仮想空間上で再現できる。
【研究拠点概要】
筑波大学サイバニクス研究センターは、サイバネティクス、メカトロニクス、情報科学を中核として、ロボット工学、脳・神経科学、IT技術、感性・人間工学、生理学、社会科学、倫理学など、人・AIロボット・情報系が融合/複合した新領域「サイバニクス」を開拓する研究拠点である。
#本インタビューの関連論文:Development of human collaborative robot to perform daily tasks based on multimodal vital information with cybernics space., A. Uehara, H. Kawamoto, and Y. Sankai, Frontiers in Robotics and AI, (Sec. Biomedical Robotics, Volume 12 - 2025, DOI 10.3389/frobt.2025.1462243)
「サイバニクス技術で誰も取り残さない社会を実現したい」
「テクノロジーで誰も取り残さない社会を実現する――これが私の研究における最大のビジョンです」
――そう語るのは、筑波大学サイバニクス研究センターの上原皓先生だ。
上原先生は、人・ロボット・情報系を融合/複合する新領域「サイバニクス」を専門とし、人協調型ロボット、細胞培養、MRI画像解析など、幅広い研究テーマに取り組んでいるが、その根底には「誰も取り残さない」という一貫した考え方がある。
「科学技術と医療の急速な発展により、年齢や障害によらない社会参画や生活様式の多様化が進んでいます。運動・身体特性やライフスタイルが異なる多種多様なユーザーの、時々刻々と変化する状態に対し、サイバニクス技術により心身の自立度向上が実現できると考えています」
その実現に向けて、上原先生が焦点を当てているのは、神経筋疾患によって生じる生活上の困難だ。
「まずは神経筋疾患で自立した生活が難しい方々を対象として研究を進めています。最も困難な状況にある方々を支援できる技術を開発すれば、その技術は健常者や子供、高齢者など様々な方にも応用できます。最初に最も厳しい状況へアプローチすることで、結果的に技術の適用範囲を広げられると考えています」
こうした考えのもと、上原先生はデジタルツイン技術を活用した新しいアプローチで、生活支援の可能性を切り拓いている。研究においては「現場主義」を徹底し、患者やそのコミュニティとのつながりを大切にしながら研究開発を進める――この姿勢が、上原先生の研究の原動力となっている。
【研究の背景】人・ロボット・情報系を融合/複合する新領域「サイバニクス」
サイバニクスという学術領域について、上原先生は次のように説明する。
「サイバニクスは、人・ロボット・AI・情報系を融合/複合した新しい学術領域です。約30年前に山海嘉之教授が提唱されたもので、この研究室を中心として脈々と開拓されてきました」
この分野が生まれた背景には、社会が直面する課題の複雑さがある。
「社会が本当に抱えている問題は、工学部の歯車やリンクといった単一の領域だけでは突破が難しい。様々な分野の融合や複合を通して、実問題を解決していこうというのがサイバニクスの出発点です」
また、サイバニクスの語源は、サイバネティクス(制御と通信の学問体系)にあるが、決定的な違いがあるという。
「サイバニクスは人中心であることが大きな特徴です。基礎研究か臨床研究かというと、答えは両方です。我々は『基礎と実際』をセットで進めることを重視しています。人を中心に置き、医学をはじめとする関連領域を組み合わせていきます。さらに、研究室で論文を書いて終わりではなく、科学技術を社会に還元することがゴールです。実際に社会にどう技術をインストールしていくかまで考える必要があります」
一般的に研究室では論文執筆が主な活動とイメージされることも多いだろう。しかしサイバニクス研究センターでは、技術の社会還元、ルール整備、人材育成、経済サイクルまでを同時展開する――この包括的なアプローチこそが、この研究拠点の大きな特徴である。
【デジタルツインの活用】NVIDIA Omniverseで実現するサイバニクス空間(「人」+「サイバー・フィジカル空間」)
上原先生の幅広い研究テーマの中でも、本インタビューではNVIDIA Omniverseを活用したサイバニクス空間(「人」+「サイバー・フィジカル空間」)の構築に焦点を当てる。
「サイバニクスは実社会が直面する複雑な課題の解決に向けて開拓されている、人を中心とした領域です。人情報を軸に従来のデジタルツインを発展させることで、サイバニクス空間を構築することが自然であると考えました」
NVIDIA Omniverseは、NVIDIAが提供する仮想コラボレーションとリアルタイムシミュレーションのためのオープン プラットフォームである。物理シミュレーションとレンダリングをGPUで高速に実行でき、複数のアプリケーションやユーザーがリアルタイムで同じ3D空間を共有・編集できることが特徴だ。

NVIDIA Omniverseの全体構成イメージ(参考:NTTPC)
産業用途では製造業のデジタルツイン構築、建築設計、自動運転シミュレーションなどに活用されているが、上原先生はこれを人協調型ロボット研究と生活支援に応用することを試みている。このアプローチの重要なポイントは、サイバー空間だけで完結させず、フィジカル空間で人やロボットが実際に相互作用することにある。いわゆる「フィジカルAI(物理AI)」として、現実世界の物理法則に基づいて動作し、人間と協調できるロボットシステムの実現が求められている。
そのためには、人のマルチモーダルなバイタル情報の取得やロボットの制御をリアルタイムで行う必要があった。
「これまでは何かを身につけて動きを支援することや、バイタル情報をセンサーで取るといった研究をしてきました。しかし、生活様式が多様化し、時間や空間に関係なくインタラクションする必要が出てきました。そこでデジタルツインのプラットフォームを中継地点として活用し、離れた場所にいる人、様々なロボット、IoTデバイスを有機的につなぐことを考えました」
このように上原先生は、サイバニクス空間(「人」+「サイバー・フィジカル空間」)を“仮想の世界”に閉じず、現実とデジタルがつながり合う新しい環境としてとらえ、人がその間を自由に行き来できる未来を見据えている。
NVIDIA Omniverse選定の理由
また、様々なプラットフォームを検討した中で、NVIDIA Omniverseを選んだ理由を伺った。大きく4つの決め手があるという。
1. 拡張性と連携性
「既存のアプリケーションとの連携がしやすい構造が最大の決め手でした。ROS ※2 やUnity ※3 など様々なプラットフォームと容易につなぎ込めます。自作のセンシングデバイスやロボットのデータを流し込んでNVIDIA Omniverseで表示したり、NVIDIA Omniverseから別のロボットを制御したりが、Pythonで自由にプログラミングできます。この融通の利きやすさはシステムの研究開発を円滑に推進する上で有意義だと考えています」
※2 ROS(Robot Operating System):ロボット制御や認識処理のためのオープンソースミドルウェア。複数のセンサーやアクチュエーターを統合し、柔軟なロボット開発を実現する。
※3 Unity:リアルタイム3D開発環境。物理シミュレーションやインタラクティブな可視化に対応し、研究・産業分野でのデジタルツイン構築にも利用されている。
2. GPUを活用した高性能処理
「NVIDIAが開発しているツールなので、並列処理・レンダリング・数値計算といったGPUの強みを最大限に活かせます。レンダリングと数値計算の両方を高い水準で実現できるプラットフォームはサイバニクス空間の基盤構築に有用だと考えています」
3. GPU仮想化による効率的なリソース活用
「NVIDIA Omniverseの大きな強みは、GPUを仮想化して複数のユーザーでシェアしながら使える点です。一箇所に大きなGPUがあれば、ハイエンドではないラップトップにも仮想的にGPUを割り当てて、手元のPCでもスムーズに動かせます。これを実現するには高速な通信プロトコルが必要ですが、センター内で整備されているPCoIP(PC over IP)という映像レンダリングに特化した超高速通信プロトコルを使うことで、遅延を最小限に抑えられます」
4. ハイエンド環境とセキュリティを両立
研究センターの環境も、NVIDIA Omniverse活用を後押しした。
「当研究センターにはDGX1というNVIDIA製のスーパーコンピューターや、OVXレンダリングサーバーがあります。患者さんの個人情報も扱うため、外部のクラウドサービスではなく、学内のサーバールームで閉じた環境で研究を進められることも重要でした」

個人情報や秘匿情報を扱う研究機関・組織では、セキュリティ確保の観点からオンプレミス環境が不可欠だ。ハイエンドな計算資源とセキュアな環境を両立できたことが、NVIDIA Omniverse活用の大きな後押しとなった。
サイバニクス空間の実現:フォトリアリスティックな3Dモデルの意義
NVIDIA Omniverseを選定した上原先生は、筑波大学内のサイバニクス研究棟を忠実に再現した3DモデルをNVIDIA Omniverse上に構築し、これを移動ロボットと連携させることで、物理空間とサイバー空間をリアルタイムで双方向連携するサイバニクス空間を実現した。
特筆すべきは、論文で公開された3Dモデルが非常に精密に作られている点だ。なぜここまで作り込む必要があったのか伺った。
「一般的なメタバースは、サイバー空間の中だけで完結するイメージだと思います。しかし私たちが目指すサイバニクス空間は全く異なります。サイバー空間だけで閉じるのではなく、物理空間のロボットもリアルタイムで動かせるし、人間が自分の意志でサイバー空間に入ったり、また物理空間に戻ったりできる。両方の空間を自由に行き来できることが本質です」
具体的なユースケースのひとつとして、高齢者施設や在宅ケアサポートでの活用を想定している。
「例えば、身体的な制約により外出が難しい方が『散歩したい』と思った時、自分の意志でサイバー空間に入って施設内や屋外を歩き回り、気分転換できます。またすぐに物理空間に戻って、『喉が渇いた』と思ったらロボットに飲み物を取りに行かせて口元まで持ってこさせる。このように、物理空間とサイバー空間をシームレスに行き来しながら、自立した生活を支援するアプリケーションを想定しています。そのため、サイバー空間でもリアルな体験ができるよう、フォトリアリスティックに作り込んでいます」
現在は、物理空間のロボットのデータをNVIDIA Omniverseにほぼリアルタイムで送信し、サイバー空間内でも同期して動作させる仕組みが実現できている。今後は、この基盤をさらに発展させ、人の動きや状態もデータ化して解析する機能を追加していく予定だ。
実装プロセスと実際の使用感:6〜7ヶ月での原理検証
では、このサイバニクス空間はどのように構築されたのだろうか。3Dモデルの作成から実証実験まで、約6〜7ヶ月という比較的短期間で原理検証を達成できたという。
「建物の実寸大3Dモデルを外部の協力も得ながらNVIDIA Omniverse上に構築しました。並行して、プリセットのサイバー空間を使って手元の移動ロボットとの連携テストを進めていました。3Dモデル作成から実証実験まで合わせて6〜7ヶ月程度です」
実際に使用してみて、選定時に期待していた拡張性と高性能処理の強みを改めて実感したという。
「拡張性が良かったです。Pythonで自由にプログラムを書いて調整できるので、研究の自由度が非常に高い。融通が利いて、かつ高品質なレンダリングや数値計算もできるという組み合わせは、効果的に研究開発を推進する上で有効だと思います」
一方で、最先端プラットフォームならではの留意点もある。
「NVIDIA Omniverseは日々進化しているプラットフォームです。数日前まで使えた機能が変更されたり、新機能が追加されたり、関数名が変わったりすることがあります。コミュニティで公開されている情報も常にアップデートされるので、最新情報のキャッチアップが必要です。ただ、これは逆に言えば、常に新しい機能が追加されて可能性が広がっているということでもあり、楽しいところでもあります」
このような試行錯誤を経て、物理空間とサイバー空間をリアルタイムで双方向連携するサイバニクス空間の基盤が構築された。しかし上原先生にとって、これはあくまでスタート地点に過ぎないという。
【今後の展開】社会実装へ向けた挑戦と新産業創出への道
上原先生の研究は、技術開発にとどまらない。上原先生が目指すのは、包括的メディカル・ヘルスケアの実現と新産業の創出だ。
「自宅での予防や自立支援から、病院や施設でのリハビリテーションまで、医療と非医療が相互に連携・融合してシームレスに接続される包括的メディカル・ヘルスケアを目指しています。サイバニクス技術を研究室の中で基盤技術として閉じるのではなく、社会実装、ルール整備、人材育成、経済サイクルも同時展開することで、ロボット産業、IT産業に続く新産業『サイバニクス産業』を創出したい。超高齢化する人、そして社会へと貢献していきたいと考えています」
このような社会実装には、新しい技術分野のルール整備が不可欠だという。
「デジタルツインについても、医療や生活支援・福祉に関する規格はほぼない状態です。自分たちでルールを作るところから始める必要があります」
HALが医療保険適用を実現したように、今回の技術も公的保険適用を目指し、ケーススタディやコホート研究を通じて社会的コストを下げられることをデータで示していく必要がある。
基礎研究から社会実装、ルール整備、そして新産業創出へ――。上原先生が描くサイバニクス技術の未来は、研究室の枠を超えて社会全体を変革する可能性を秘めている。NVIDIA Omniverseを活用したサイバニクス空間の構築は、技術開発の成果にとどまらず、高齢者や非健常者の自立支援、介護人材不足の解消、医療・介護コストの最適化といった社会課題の包括的な解決策となる。「誰も取り残さない社会」の実現に向けた上原先生らの挑戦は、人、物理空間、サイバー空間が融合/複合する新しい時代の幕開けを告げている。
___________________________________________________________________________________
NVIDIA Omniverseの導入・活用をご検討の方へ
NVIDIA エリートパートナーであるNTTPCは、NVIDIA Omniverseの導入・検証をサポートしています。NVIDIA技術の活用法や技術的なご相談など、お気軽にお問い合わせください。
※HALはCYBERDYNE株式会社の登録商標です。
※Unityおよび関連の製品名はUnity Technologiesまたはその子会社の商標です。
※NVIDIA、NVIDIA Omniverse、NVIDIA OVX、NVIDIA DGX-1は米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。
※本記事に記載された情報は、リリース時点のものです。
商品・サービスの内容、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。