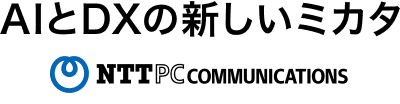AI時代に求められるマーケター像とは?NTTPC×シナプスが語る“人とデータ”の融合|シナプス×NTTPCが考えるマーケティングの神髄

デジタルを使ったコミュニケーションが進化する今、企業の価値を高めるマーケティングはどうあるべきだろうか。マーケティングのコンサルティングサービスを提供する株式会社シナプス代表取締役社長の後藤匡史氏と、NTTPCでCMO(最高マーケティング責任者)を務める佐村俊幸が考えるマーケティングとは。


現場経験や顧客目線意識がマーケターには重要
佐村:マーケティングは企業活動や事業戦略において重要な役割を担っています。また、近年はデジタルチャネルやデジタルツールを活用したデジタルマーケティングも盛んです。さらに、企業活動から得たデータをマーケティングにどう生かしていくか、生成AIをどう利用するかといった課題もあります。
そこで本日は、マーケティングに詳しい株式会社シナプス(以下、シナプス)さんの後藤社長をお招きして、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。まずはシナプスさんの事業概要について教えてください。
後藤:シナプスはマーケティング領域のコンサルティングからスタートした会社です。企業のマーケティング活動を支援するとともに、マーケティング人材を育成する活動も行っています。お客さまの業種は幅が広くて、食品、エンタメ、化粧品などのBtoCの企業や、医療、農業、工業などのBtoBの企業とお付き合いがあります。
佐村:マーケティング活動を進めるうえで、マーケターと呼ばれる人材の育成はとても重要だと思います。御社の事業として人材育成のサポートもされているとのお話がありましたが、私自身、普段の仕事の中で若手のマーケターをどう育てるかがいつも悩みどころです。育成のポイントがあれば教えていただけますか?
後藤:すごく難しいですがいい質問ですね。一般的な人材育成の考え方として「7・2・1の法則」が知られていて、7割は現場の経験、2割は上司や顧客からのフィードバック、1割は学習やトレーニングと言われています。私の体感値もそのとおりで、現場経験はとても大きいと感じます。とくにマーケターの場合、自分が進めた施策に対して効果が出ているかどうかがデータを通じて検証しやすいので、その体験をどれだけ積んでいくかですし、上司やお客さまからのフィードバックから得られるものも大きいわけです。
一方で、マーケティングのセオリーはきちんと学習して理解しておかなければなりません。そのバランスをどう与えていくかがポイントになると思いますね。
逆に私から質問ですけど、現在 NTTPCコミュニケーションズ株式会社(以下、NTTPC)のCMOを務めていらっしゃる佐村さんは、これまでマーケターとしてどのように成長されてきたのでしょうか。

佐村:成長できているかどうかはさておいて、自分の目線とか社内の目線ではなくて、お客さまの目線をどれだけ意識の中に置けるかを原点にしています。たとえばテレビを見ていても今の消費者の興味がどこにあるのかを感じようとしたり、我々の事業ドメインのICT領域においてもお客さまの興味・関心はどこにあるのだろうと常に考えるということですね。後藤さんが言われた、現場でお客さまと接することが重要というお話とも通じるかもしれません。
後藤:顧客視点とよく言いますが、とくにBtoBの業界にとってはとても難しい問題です。マーケティングの研修でケーススタディとしてBtoCの事例を取り上げると受講者の理解がいいんですが、BtoBを取り上げると個人としての消費体験がないので皆さんキョトンとされるんですね。その業界のことが分かってくるとBtoBも面白いんですけどね。
佐村:まさしくその通りですね。
マーケティング活動全体を支えるデジタルマーケティング
佐村:近年のマーケティング活動ではデジタルチャネルやデジタルツールを活用することが当たり前になっています。NTTPCでも、デジタルチャネルを使ってソリューションを訴求し、お客さまからいただいた問い合わせなどのリード情報は、CRM基盤に集めて、MAツールや名刺管理ツールなどと連携させています。新規販売から最終的にはカスタマーサクセスへとつなげています。そういったいわゆる「デジタルマーケティング」を後藤さんはどう捉えていますか?
後藤:コンサルティングのお客さまに対してデジタルマーケティングの話をするときには、まずマーケティングとは何か、というところからスタートするようにしています。シナプスではマーケティングを「顧客ニーズへの適合と競争優位を構築する活動」と定義していて、要はお客さまのニーズに合わせて、競争優位を作って、結果的にビジネスを大きくしていくことがマーケティングの目的としてまずあって、それを踏まえたうえで、ここ20年ぐらいのデジタルの進化によってデジタルマーケティングがとても大きなものになっている、といったことを理解していただくようにしています。
佐村:なるほど。後藤さんが普段接しているそういったお客さまは、マーケティング全体とデジタルマーケティングとを、どういった組織で扱おうとしているのでしょうか?
後藤:デジタルを扱おうとすると専門性が必要になりますから、デジタル部門とマーケティング部門とを分けている会社さんもありますし、ひとつの部署で両方を扱っている会社さんもあります。ただ、組織によらずマーケティング活動は一気通貫でやらないといけないよね、ということは皆さん意識されていますね。
ところで、佐村さんには以前当社のマーケティングセミナーで講演をしていただいたときに、組織も含めたインサイドセールスの改革によって受注を2倍にしたというお話をされていましたね。
佐村:営業部門における役割をフィールドセールスとカスタマサクセスに明確に分け、マーケティング部門はインサイドセールス(*)も担当するなどの組織変更を2020年7月に行いました。マーケティング部門は広告や宣伝に始まり、インサイドセールスでお問い合わせいただいたお客様の課題をヒアリングしながら関係を構築し、見積書を提出するなどが必要となった段階で営業部門に引き継ぐところまでを役割としました。
ただし、営業部門とマーケティング部門は「受注額」という同じKGIを設定し、常に同じ目線で動くことを徹底することで、新規の受注を2倍に伸ばすことができました。今はさらに踏み込んで、営業部門に引き継いだ案件が実際に受注に至るまでのフォローにも範囲を広げています。デジタルマーケティング活動を拡張するという意味で「エクステンション・デジタルマーケティング」と呼んでいます。
後藤:プロセスの途中を指標化したKPIではなくて、プロセスのゴールを指標化したKGIでビジネスを評価し受注額の達成責任を担っているというのは、最終的にはビジネスを大きくしていくことが目的であるマーケティングとして結構本質的だと感じました。
インサイドセールス:主にオンラインを通じて顧客とコンタクトし成約へとつなげる営業活動。内勤営業。
データの共有と一元化がビジネス拡大やDXの鍵
佐村:われわれがインサイドセールスの改革を進めるにあたって苦労したのがデータの共有と一元化でした。マーケティング部門以外に、営業部門と、プロダクトを開発する部門がありますが、最初はCRMにデータがなかなか集まりませんでした。具体的なお客さま案件などのパイプラインが今どれくらいあるのか、どれぐらいが受注に至ったかなどが見える化されるにつれて社内での理解も進み、ようやくすべてのデータがCRMに乗るようになってきました。

後藤:使い慣れた環境から動きたくないという気持ちが働きやすいこともあり、データの共有化と一元化はどこの企業も悩まれていますね。当社がDX(*)を支援している企業でも最初にボトルネックになるのがデータの統合です。
データはあるけど使えない状態になっていることもあるので、DXの前にまずはETL(*)をしっかりやりましょうと。企業の体質にもよるかもしれませんが、データや基盤に投資をして、きちんとした運用ができるかどうかがとても重要と感じます。
佐村:実感としてよくわかります。私どももデータを集めるところは苦労しました。会社のために必要ということを説いて回らないといけないのだろうと思います。さて、データが集まってくると、次はそれらを企業活動に生かそうとなるわけですが、世の中の企業がデータをどう活用しているのか、後藤さんの実感を教えてください。
後藤:BtoCだとデータを集めて活用しているデータリッチな業界はたくさんあります。医薬品や消費財のメーカーなどがそうで、ドラッグストアなどからPOS(*)データを購入して、商品がどこでどれぐらい売れているかを把握しています。
BtoBはパンデミックの前後でずいぶん変わりました。一時期は対面での営業活動ができませんでしたから、どの会社もインサイドセールスやデジタルコミュニケーションに投資をしたと思います。ただ、ツールやデータを活用できているかどうかには会社によって差があって、データはあっても使える状態になっているかどうかは結構分かれますね。
DX:Digital Transformation。企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。(経済産業省による定義)
ETL:Extract, Transform, Load:複数のデータソースからデータを抽出(extract)し、変換(transform)し、格納(load)すること、またはそのツール。
POS:Point of Sales。販売時点情報管理システム。
マーケティングやインサイドセールスにも生成AIを活用
佐村:マーケティングにも生成AIを活用しようということで、お客さまから見積もりが欲しいと言われたときに、以前はインサイドセールスから営業に案件を引き渡し、営業から見積書を提出していたのですが、生成AIを使って概算見積額を即座にインサイドセールスから出すようにプロセスを見直しました。
そのため受注率が高まるなどの直接的な効果も生まれています。生成AIはそのほかにもいろいろな可能性をもたらしますが、シナプスさんではどう活用されていますか?
後藤:コンサルタントとして、マーケティング戦略構築支援の際に、ターゲット顧客を絞るために、ペルソナを決めて全員でイメージを共有することがあります。たとえば若い女性で、こういう服を着ていて、などを口頭で説明するのですが、結局のところ聞いている側の印象によりそれぞれ違うペルソナになってしまうことがあるのです。
そこで、想像していた人物像を生成AIに与えて画像として出力させるようにしました。すると、それぞれがイメージしていたのとちょっと違うね、みたいな具体性が湧いてきます。この手法はよく使っています。
佐村:なるほど、それは面白い。
後藤:この話はあまり言っていないのですが、実は大学院時代にデータマイニングの研究をしていました。生成AIやディープラーニングが登場していない時代で、サポートベクターマシン(SVM)というパターン認識アルゴリズムが出てきた時代で、インテルのCPUを回しながらやっていました。それが今はGPUが出てきて、業界に詳しい人によるとハードウェアの物量勝負になっているという話を聞きます。
佐村:そういう側面はもちろんありますね。最近ではNVIDIA社が「NVIDIA DGX Spark」というGPUパソコンとも呼べるようなコンパクトサイズのハードウェアを、かなりの低価格で出してきたことで、ずいぶん身近になりそうです。「NVIDIA DGX Spark」を取り扱っているNTTPCにも研究機関や様々な企業の方からお問い合わせをたくさんいただいていています。こういうハードウェアが普及すると生成AIの在り方もまた変わってくるかもしれません。
後藤:生成AIって進化が速くて、登場した頃はプロンプトをどう書くかって一生懸命やっていましたが、今は自然言語で普通に書けばそれなりの答えが返ってくるじゃないですか。だから先が読めないですけど、ということはどう先を読むかよりも、生成AI活用に投資して自分たちで作っていくかの方が大事なんじゃないかというのが私の仮説で、たぶんその仮説は正しいんじゃないかなと思っています。
佐村:おっしゃるとおりで、NTTPCとしてもお客さまにもそうした提案をどんどん差し上げていきたいなと思っています。
AI時代のマーケターの役割は顧客理解・人間理解
佐村:最後にデジタルマーケティングの将来像についてお話を聞かせていただければと思います。生成AIの活用も広がっている中で、デジタルマーケティングはこの先拡大していくのか、それとも当たり前のものになってデジタルマーケティングという言葉自体がなくなっていくのか、どう捉えられていますか?
後藤:興味深い質問ですね。今や人類はデジタルから逃れられなくなっているので、企業のマーケターにとってデジタルを使わないという選択はなくて、一方でアナログやリアルの世界でもやるべきことはまだいっぱいあるので、デジタルと融合した状態が当たり前になっていくだろうと思います。
佐村:なるほど。デジタルマーケティングって、マーケティング活動の中の一つのツールというかアプローチみたいな感じになっていて、将来的に言葉としてはもしかしたら消えるかもしれないけど、ずっと続いていくという感じですかね。
後藤:そうだと思います。ただ、シナプスの社内でもよく話をしますけど、コンテンツマーケティングで言えば、ちゃんとしたコンテンツや記事を作ることが大切で、みんなが読みたい記事を作れば誰にとってもハッピーで、SEO(*)やAIO(*)のような対策の意味がどんどん薄くなっていって、最後は本物が残る時代になるだろうと。
そのときにマーケターは何をすればいいかというと、結局はお客さま理解・人間理解に収れんしていくだろうというのが私の見方でもあるし、多くのマーケターの見方でもあると思っています。
佐村:ありがとうございます。お客さま理解・人間理解に収れんするというのはとても示唆に富んだ考えと感じました。今日はシナプスの後藤社長をお招きして、デジタルマーケティング、データ活用、生成AI、そしてそれらの将来像まで幅広くお話しいただいて、私自身とても勉強になりました。今日はお忙しいところありがとうございました。
SEO:Search Engine Optimization。自社のコンテンツが検索エンジンの上位に表示されるようにウェブページを最適化すること。
AIO:AI Optimization。自社のコンテンツが生成AIによる検索結果(回答)で引用されるようにウェブページを最適化すること。